PR会社のホワイト企業、正直なところ…
PR会社のホワイト企業って、どうやって見分けるんですか?ってよく聞かれるんだけど、うーん、これ、すごく難しい質問なんだよね。まず最初に言っておくと、「完璧なホワイト企業」っていうのは、この業界にはほぼ存在しないかもしれない。ごめん、いきなり夢のない話で。
でも、絶望する必要はなくて、「自分にとって限りなくホワイトに近い、働きやすい会社」を見つけることはできる。それがゴールかなって、個人的には思ってる。キラキラしたイメージとは裏腹に、実際はかなり泥臭い仕事が多いし、クライアントとメディアの板挟みになることも日常茶飯事。だからこそ、会社の「体質」がすごく大事になってくるんだよね。
ネットの情報だけじゃわからない、本当の見分け方
ネットで「PR会社 ホワイト」って検索すると、だいたい「残業時間」とか「年間休日」とか、そういう求人票でわかる情報が出てくるよね。 もちろんそれも大事。大事なんだけど、それだけだと本質は見えてこない。特にPR業界は、数字に現れない部分に「働きやすさ」が隠れてたりするから。
例えば、離職率が高いのはPR業界の特徴の一つだって言われることもある。 実際、人の入れ替わりが激しい会社もあるのは事実。 でも、それが全部ネガティブかっていうと、そうでもない。スキルを身につけて、もっと良い条件の会社や事業会社の広報にステップアップしていく人も多いからね。だから、離職率の数字だけ見て「この会社はブラックだ」って決めつけるのは、ちょっと早いかなって思う。
じゃあ、どこを見るべきか。僕が大事だと思うのは、もっと「中身」の部分。例えば、どんなクライアントと仕事をしているか、とか。会社の評価制度がどうなってるか、とか。そういう、外からは見えにくい部分にこそ、その会社の本質が隠れてるんだよね。

具体的なチェックポイント、これだけは押さえて
じゃあ具体的に、どうやってその「中身」を見ていくか。僕がもし今、転職活動するなら、こんなところをチェックするかな。
求人票の裏を読む
まず、求人票。ここにもヒントはたくさんある。「裁量労働制」っていう言葉、よく見るでしょ? これ、聞こえはいいけど、実際は「みなし労働」だから、長時間労働の温床になりやすいっていう側面もある。 もちろん、本当に自分の裁量で働ける素晴らしい制度として機能している会社もある。 大事なのは、その実態。面接で「裁量労働制とのことですが、実際に皆さんは何時ごろに退社されることが多いですか?」みたいに、具体的な働き方を聞いてみるといい。2024年4月から制度が少し変わって、本人の同意が必要になったりしてるから、その辺の対応がちゃんとしてるかもポイントだね。
面接は「質問する場」と心得る
面接は、自分をアピールする場であると同時に、会社を「見極める」絶好の機会。受け身になっちゃダメ。僕だったら、こんな質問をするかな。
- 「これまでで一番大変だったプロジェクトについて教えてください。それをどう乗り越えましたか?」
この質問で、会社のカルチャーが見えてくる。トラブルが起きた時に、個人に責任を押し付けるのか、チームでサポートするのか。その答え方で、だいぶ雰囲気がわかる。 - 「評価制度はどのようになっていますか?どのような点が評価に繋がりやすいですか?」
評価基準が曖昧だと、結局は上司の好き嫌いで決まったりして、モチベーションを保つのが難しい。明確な基準があるかどうかは、長く働く上ですごく重要。 - 「クライアントの業種は、BtoBとBtoC、どちらが多いですか?」
これも結構大事。一般的に、BtoC、特に消費財やエンタメ系のクライアントが多いと、発表会やイベントで土日出勤が増えたり、世の中の動きに合わせて急な対応が求められたりする傾向があるかな。 もちろんそれがやりがいでもあるんだけど、プライベートとのバランスを重視するなら、BtoB中心の会社のほうが落ち着いて働ける可能性はある。
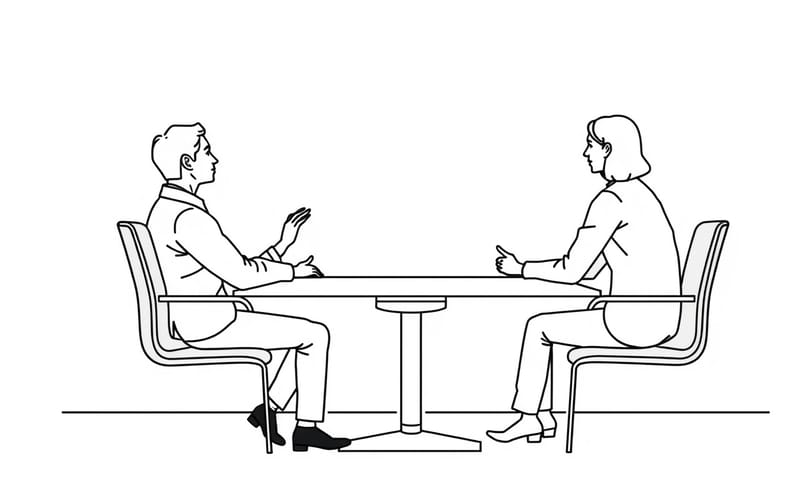
社員の「顔」と「言葉」を見る
可能なら、OB/OG訪問をしたり、カジュアル面談をお願いしたりして、現場の社員と話す機会を作りたいところ。口コミサイトも参考になるけど、あれは辞めた人の意見が多いから、ちょっと割り引いて見た方がいい。 見るべきは、悪口じゃなくて、「組織体制」や「企業文化」についての具体的な記述だね。
あと、意外と参考になるのが、アメリカの働き方との比較。アメリカの企業文化は成果主義が徹底していて、働く時間より生産性が重視されることが多い。 一方で、日本の場合はまだチームの調和やプロセスが重視される傾向があるかな。 どっちが良い悪いじゃなくて、そういう文化の違いを知っておくと、「この会社の働き方は、日本的なのか、それともグローバル基準に近いのか」っていう視点で見ることができる。外資系のPR会社なのか、日系の老舗なのかでも、雰囲気は全然違うからね。
ホワイト寄り?ブラック寄り?比較してみると…
ここで一度、僕の経験から考えた「ホワイト寄りの会社」と「そうでない会社」の特徴を、ちょっとまとめてみるね。あくまで個人的な見解だけど。
| チェック項目 | ホワイト寄りのPR会社 | ちょっと注意が必要なPR会社 |
|---|---|---|
| ナレッジ共有 | 成功事例も失敗事例も共有する仕組みがある。チームで戦う意識が強い。 |
完全に属人化してる。「あの人しか分からない」が多い。見て覚えろ文化。 |
| 評価制度 | 評価基準が具体的で、フィードバックも定期的。何を頑張ればいいか分かりやすい。 |
上司の匙加減ひとつ。声の大きい人が評価されがちで、不公平感があるかも。 |
| クライアントとの関係 | パートナーとして対等な関係を築こうとしてる。無理な要求にはちゃんと「NO」と言える。 |
完全に下請け状態。クライアントの言うことは絶対、で振り回されがち。 |
| 人材育成 | 研修制度があったり、OJTがしっかり機能してる。人を育てようという意思を感じる。 |
基本はOJTという名の放置プレイ。すぐに即戦力になることを求められる。 |
| 経営陣の考え方 | 社員の働きがいや健康をちゃんと考えてる。 働き方改革とかにも積極的。 |
「やりがい搾取」になりがち。「好きでやってるんだから」という雰囲気がある。 |
この見分け方の限界
ただ、ここまで色々話してきたけど、この見分け方にも限界はある。結局のところ、どの会社が「ホワイト」かは、人によるから。例えば、僕は多少忙しくても、大きな裁量権があって新しいことに挑戦できる環境が好きだけど、別の人は、給料が高くて残業が全くない環境の方がいいかもしれない。
それに、部署やチームによっても労働環境は全く違う。同じ会社なのに、Aチームは毎日定時で帰るけど、Bチームは終電帰り、なんてことも普通にある話。だから、「この会社はホワイトだ」って断言するのは、やっぱり難しいんだよね。

結論:自分だけの「ホワイト企業」を見つけよう
結局、大事なのは、自分が仕事に何を求めるのか、その優先順位をはっきりさせること。給料?やりがい?プライベートの時間?専門性?
完璧な100点の会社はないかもしれないけど、自分にとって「これだけは譲れない」っていう条件を満たしてくれる80点の会社なら、きっと見つかる。そのためには、今日話したみたいな、求人票の数字だけじゃない「生の情報」を集めることが、何より大事なんだと思う。
あなたの「譲れない条件」って何ですか? もしよかったら、コメントで教えてもらえると嬉しいな。



