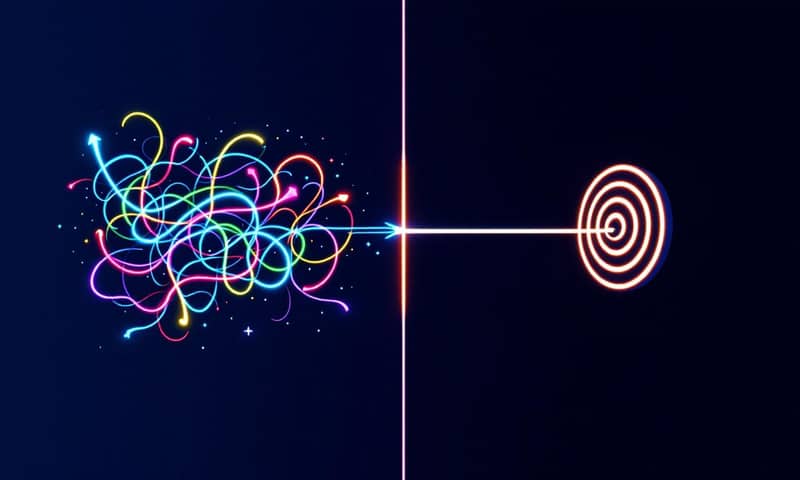えーと、今日はですね、PR会社とか広報の代理店をどうやって選ぶか、っていう話をしようと思ってて。よく聞かれるんですよ、これ。特に最近だと、日系とか外資系とか、あとグローバル展開してる大きいところとか、色々あって、もう「どれがいいんですか!?」みたいな。正直、ランキングとか見ても、あれ、あんまり意味ないときもあって…。いや、意味がないって言うと語弊があるな。えーと、参考にはなるんだけど、それだけじゃ決められない、っていうのが正しいか。
まず結論から言うと、一番大事なのは…
もうね、いきなり結論から言っちゃいますけど、PR会社選びで一番大事なのは、会社の規模とか知名度ランキングじゃなくて、「自社の事業課題をちゃんと理解してくれてるか」と「実際に手を動かしてくれる担当者が誰で、その人がどれだけ優秀か」、この二つに尽きるんですよ、本当に。 有名なPR会社にお願いしたからって、うまくいくとは限らないんです。 なんでかって言うと、プレゼンではエース級の人が出てきて「おおっ!」ってなるんだけど、契約したら、えーと、新人の子が付いちゃって「話が違うじゃん…」みたいなことが、まあ、悲しいけど本当によくある話で。 だから、「誰が」やるのかっていうのが、会社の看板よりずっと大事。これ、マジで。
なんで「誰が担当するか」がそんなに重要なのか?
ちょっと考えてみて欲しいんですけど、PR活動って、結局は人と人とのコミュニケーションなんですよね。記者さんとリレーションを築くのも人だし、こっちの事業の魅力を深く理解して、それを世の中に響く言葉に翻訳してくれるのも、人。だから、担当者の熱意とか、スキルとか、あと単純に「この会社を有名にしたい!」って思ってくれる愛情みたいなものが、成果に直結するんです。 例えば、すごくドライに「契約だからやります」っていうAさんと、「このサービス、面白い!絶対広めたい!」って前のめりでやってくれるBさん、どっちがいいかって言ったら、もう明らかじゃないですか。
僕が見てきた失敗例でいうと、KPI(目標みたいなものですね)がズレてるケースも多い。 こっちは「サービスのリード獲得(見込み客の獲得)」を増やしたくてお願いしてるのに、PR会社側は「メディア掲載数」だけを追いかけてたりとか。 そうなると、なんかファッション誌とかに載って「おしゃれな会社」っていうイメージは付くかもしれないけど、「で、売上は?」みたいな、一番大事なところが抜け落ちちゃう。これは、最初の段階で「我々のゴールはこれです」っていうのを、担当者レベルまですり合わせられてないのが原因なんですよね。
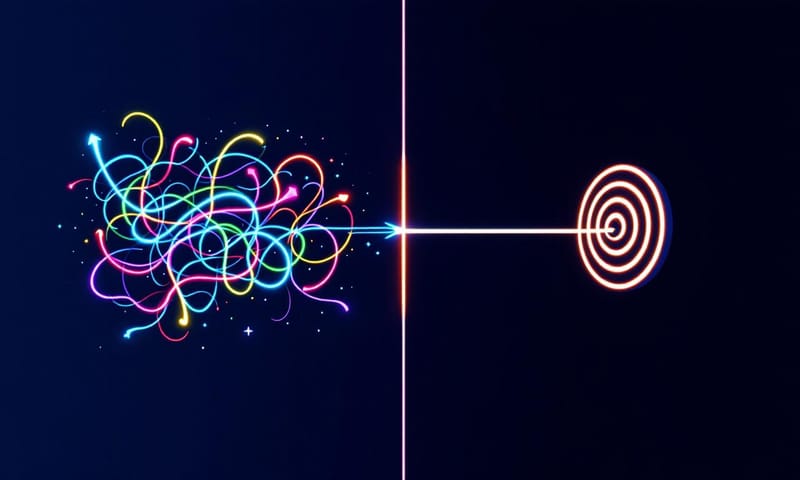
じゃあ、具体的にどうやって選べばいいの?っていうステップ
はい、じゃあ具体的にどういう手順で選んでいけば失敗しにくいか、っていう話をしますね。僕がいつもやってる方法です。
- まず自分たちの「目的(KGI/KPI)」を文章にする。
「なんでPRをやりたいんだっけ?」を突き詰めるのが最初。 例えば、「BtoBのSaaSだから、業界専門誌に取り上げられて、導入事例の問い合わせを月10件増やす」とか、「新商品を出すから、20代女性向けのウェブメディアに3ヶ月で5件以上掲載されて、指名検索数を2倍にする」とか。 ここがフワッとしてると、全部フワッとします。 - 会社の得意分野と実績を「批判的に」見る。
ホームページに載ってる実績って、まあ、当たり前ですけど成功したやつだけなんですよ。 ここで見るべきは、自社の業界とか、企業規模が近い実績があるかどうか。 ITベンチャーなのに、大手食品メーカーの実績ばっかり見せられても、ちょっと違うかなって。 あと、「この実績、どういう戦略で、どういう担当者が、どういう風にメディアと関係作って実現したんですか?」って、裏側をしつこく聞くのが大事。 - コンペや提案で「担当予定者」にプレゼンさせる。
これが一番のキモかもしれない。営業のエースじゃなくて、「もし契約したら、うちのメイン担当になる予定の人、いますか?その人に説明してほしいです」ってお願いするんです。 その人の熱量とか、こっちのビジネスへの理解度とか、質問への的確さとかを見て、「この人と一緒に仕事したいか?」を判断する。これ、本当に大事なポイントです。 - 契約形態と料金を確認する。
PR会社の料金体系って、主に月額固定の「リテイナー契約」と、プロジェクト単位の「スポット契約」があります。 大手だと月100万以上とか普通ですけど、中堅のいい会社なら月50万くらいからでも、すごくいい仕事をしてくれるところはあります。 安易に値切ると、手を抜かれる原因になることもあるので注意が必要です。 むしろ、予算内で最大限のパフォーマンスを出してくれるパートナーを探す、っていう視点が重要ですね。

【比較表】日系、外資系、グローバル系って結局何が違うの?
これもよく聞かれるやつですね。ざっくり、僕の肌感覚で言うとこんな感じです。あくまで傾向ですけどね。
| 種類 | 強み(メリット) | 注意点(デメリット) | どういう会社に向いてる? |
|---|---|---|---|
| 日系PR会社 | 国内メディア、特に新聞・テレビの古くからの記者さんとの関係が深いことが多い。 日本特有の「空気感」を読むのがうまい。 |
デジタルやSNSの最新手法に疎い場合も、まだあるかな…。あと、海外展開の話になると途端に弱くなったり。 |
とにかく国内の認知度を上げたい、伝統的なメディアにしっかり載りたいっていう日本の会社。 |
| 外資系PR会社 | グローバルで使われてるPRのフレームワークとかツールが使える。 あと、レポートラインが海外本社にある会社だと、本国への報告がしやすい。ロジカル。 |
良くも悪くもドライで、マニュアル通りというか。 日本のメディアのウェットな関係構築が苦手な人もいる印象。あと、意外と担当者がすぐ辞めたり変わったりする…。 |
外資系企業の日本法人とか、海外に事業展開していて、グローバルでPR戦略を統一したい会社。 |
| グローバル大手 (エデルマンとか) |
世界中に拠点があって、多国籍キャンペーンをやるならやっぱり強い。 ブランド力も資金力もある。まあ、スター選手揃いって感じですかね。 |
とにかく高い! あと、大きい会社だと、自社みたいな小さいアカウントは若手に回されるんじゃないか…っていう不安は常にある。 |
世界規模で同時にプロモーションを仕掛けたい、予算も潤沢にある大企業。もう、体力勝負ができる会社向けですね。 |
ありがちな失敗パターンと、その対策
これまでの話とちょっとかぶる部分もあるけど、大事なのでまとめます。こういう落とし穴にはまらないように気をつけてください。
- 失敗1:丸投げしちゃう。
「プロにお願いしたから、あとはよろしく!」は一番ダメなパターン。 PR会社はパートナーであって、魔法使いじゃないんです。自社の情報とか、ネタの元とかを積極的に提供しないと、彼らも動きようがない。 - 失敗2:成果が出ないのを、すぐ会社のせいにする。
もちろん、提案がないとか、動きが鈍いのは問題外ですけど 、「今月、掲載ゼロでしたね(怒)」みたいに言う前に、じゃあ「どうやったら来月載るか、一緒に考えましょう」っていうスタンスが大事。 伴走してくれる姿勢があるかどうかが、良い会社を見極めるポイントでもあります。 - 失敗3:「有名な会社だから」で選んじゃう。
もう何度も言ってますけど、これ。自社の規模や業種、目的に合っているかが一番重要です。 ベンチャー企業が大手の総合PR会社に頼んでも、ノウハウや費用感が合わないことが多いですよ。
ちょっと待って、海外と日本じゃ選び方の基準って違う?
これ、面白いポイントなんですけど、ちょっと違いますね。例えば、アメリカのPRSA(Public Relations Society of America)っていう、まあ業界団体みたいなところのガイドラインを見ると、「まずビジネスゴールを明確にしろ」って書いてある。 これは日本も同じ。でも、彼らが次に強調するのは、実績とか専門性、あと提案内容のロジック。すごく合理的。
一方で、日本の場合は、日本パブリックリレーションズ協会(PRSJ)のガイドラインとか見ても、もちろん倫理規定とかはあるんだけど、現場レベルではやっぱり「メディアとのリレーションの深さ」みたいな、ちょっとウェットな部分がまだ重視される傾向があるかなと。 海外だと「このデータに基づいて、この媒体にアプローチするのが合理的です」ってなるのが、日本では「あの雑誌の〇〇さんとは長年の付き合いだから、一回話聞いてくれるよ」みたいなのが、いまだに結構効いたりする。どっちが良い悪いじゃなくて、そういう文化の違いがあるってことです。だから、外資系の会社を選ぶときは、日本のメディア文化をちゃんと理解してるチームかどうかも見た方がいいですね。

というわけで、まあ、色々話しましたけど、結局は「信頼できるパートナーを探す旅」みたいなものなんですよ、PR会社選びって。 ランキングや見た目の派手さに惑わされずに、ちゃんと自分たちの会社のことを考えて、一緒に汗をかいてくれる人を見つけるのが、一番の近道だと思います。
皆さんは、代理店を選ぶとき、何を一番重視しますか?もしよかったら、コメントとかで教えてください。