まず、結論から言うと…
えーと、外資のPR会社についてですね。よく聞かれるんですけど…。まあ、ひとことで言うなら、「グローバル基準の物差し」が欲しいときに選ぶものかな、って思います。別に、海外展開するから、とか、そういう単純な話だけじゃなくて。日本のやり方とは、良くも悪くも、考え方のOSが違う感じ。そこが合うかどうかが、正直、すべてな気がしますね。
だから、ただ「有名だから」とか「カッコよさそうだから」で選ぶと、多分、失敗します。ええ。まあ、そのへんを、これから少し、僕なりに話してみようかなと。はい。
なんで「外資系」をわざわざ選ぶの?
そもそも、なんで日系じゃなくて、わざわざ外資を選ぶのか。これ、クライアントが外資系の日本法人だから、ってだけじゃないんですよね。最近は、純粋な日系企業でも、あえて外資を選ぶケース、あります。なんでかっていうと…うーん、いくつか理由があるかな。
ひとつは、全世界で同時に同じメッセージを出したいとき。まあ、これは分かりやすいですよね。新製品のローンチとか。でも、もっと大きいのは、ESGとかDE&Iみたいな、世界共通のテーマで広報したいとき。こういうのって、やっぱり欧米の方が議論が進んでて、その文脈をちゃんと理解した上で、日本の市場にどう伝えるかっていう戦略を立てるのが、彼らは上手いんですよ。
あと、これはちょっと内側の話ですけど、メディアへのアプローチが根本的に違う。日本には、ご存知の通り「記者クラブ」っていう、独特のシステムがありますよね。 日系のPR会社は、そこのお作法とか、人間関係をすごく大事にする。それはそれで、すごい強みなんですけど。外資は、もうちょっとドライというか…記者クラブに属してないフリーのジャーナリストとか、海外メディア、あるいは直接ネットメディアにアプローチしたりする。その辺の考え方が、結構違いますね。

日系と外資、僕が感じた一番の違いは「空気感」
違いはいろいろあるんですけど…一番は、やっぱり「空気感」かな。コミュニケーションの仕方、というか。日系の代理店だと、やっぱり「根回し」とか、周りの合意をゆっくり作っていく感じが、まだ強いかなって思います。阿吽の呼吸、みたいな。
外資は、もっと直接的。ロジックとデータで話す感じ。 これはプランです、これがKPIです、質問はありますか?って。会議は意思決定の場で、進捗共有だけのためには、あんまりやらない。あと、ブリーフィングノートとか報告書とか、何でもテンプレート化されてて、すごくシステマティック。 最初はちょっと冷たい?って思うかもしれないけど、慣れると、ものすごく効率的ではあります。どっちが良いとかじゃなくて、本当にスタイルの違いですね。
| 観点 | 日系PR会社(僕のイメージ) | 外資系PR会社(僕のイメージ) |
|---|---|---|
| メディアリレーション | 記者クラブとの長年の付き合い。担当記者と飲んだり、人間関係で深く食い込む感じ。ある意味、ウェット。 | ニュースバリューが全て、って感じ。データで「これは記事にする価値がある」と説得する。記者クラブ以外も積極的。 結構ドライ。 |
| コミュニケーション | 定例会で顔を合わせて、じっくり話す。メールより電話とか。まあ、会社によるけど、まだそういう傾向はあるかな。 | 基本メールかチャット。要件がはっきりしてる。ミーティングはアジェンダがしっかり決まってて、短時間で終わらせようとする。 |
| 提案のスタイル | 過去の成功事例とか、経験則に基づいた提案が多い印象。「あの時のあれ、うまくいったんで」みたいな。 | グローバルでの類似ケースとか、市場データとか、とにかくファクトを固めてくる。提案書も分厚いことが多い気がする。 |
| 評価指標(KPI) | 掲載件数とか、広告換算費とか。昔ながらの指標がまだ大事にされてるかなあ。もちろん、最近は色々変わってきてるけど。 | メッセージの浸透度とか、ウェブサイトへの流入数とか、ビジネスへの貢献度をすごく細かく見てくる。レポートもめちゃくちゃ細かい。 |
| コスト感 | プロジェクト単位とか、月額リテナーでも柔軟に対応してくれるところが多い。まあ、ピンキリですけど。 | 基本はリテナー契約で、最低金額も高めに設定されてることが多いかな。時間単価(タイムシート)で管理してるところも。 |
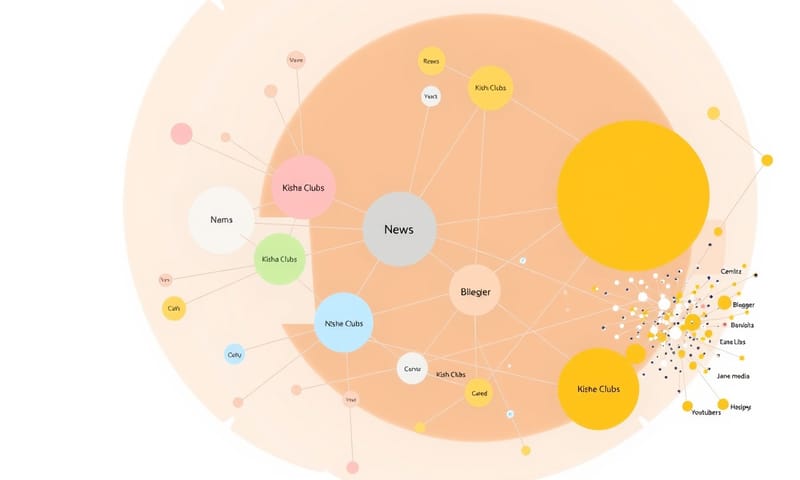
じゃあ、どうやって選ぶ?僕なりのポイント
はい。で、じゃあどうやって選ぶんだ、っていう話。よくあるチェックリストみたいなのは、まあ、あるんですけど、それよりまず、自問自答するのが先かなと。
「そもそも、なんでPR会社を探してるんだっけ?」って。本当の課題は何か、っていう。例えば…
- 自分たちのメッセージが、どうも日本ローカル過ぎて、海外に響いてない感じがする。
- 今のやり方が、ちょっと古くて、スピード感がない気がする。
- うちは外資だから、日本のメディアの慣習がよく分からなくて、いつも空回りしてる。
この「なぜ」がはっきりすれば、自ずとどっちのタイプが合うか、見えてくるはずです。その上で、実績を見る。でも、会社の名前だけで選ばないで、「実際に誰が担当してくれるのか」を絶対確認した方がいい。 特に外資は人の入れ替わりが激しいこともあるんで、契約時のエースがすぐいなくなっちゃった…なんてことも、まあ、なきにしもあらず、なので。
あとは、とにかく話してみること。最低でも2、3社。僕がさっき言った「空気感」が、自分たちの会社と合うかどうか。社内がすごいウェットな人間関係で成り立ってるのに、超ドライで合理的な外資と組んだら、多分、お互い不幸になるだけなので…。はい。
失敗しないための、ちょっとした注意点
いくつか、気をつけてほしいことがあって。ひとつは、「外資の日本オフィス」問題。グローバルでは超有名なファームでも、日本法人は数人しかいない、みたいなことがあるんですよ。そうなると、結局、日本のメディアとの深いリレーションはあんまり持ってなかったりする。名前だけで判断しちゃダメですね。
それから、これが「Localization Delta」ってやつですけど…。海外のメディアとかEUなんかは、日本の記者クラブ制度を「閉鎖的だ」って、昔から批判してることがあるんです。 で、外資のPR会社は「我々は記者クラブに頼らない、もっとオープンなやり方です」って言ってくることがある。それは魅力的に聞こえるんですけど、じゃあ、記者クラブに入ってるからこそ得られる情報とか、関係性っていうのを、本当に捨てていいのか?っていうのは、よく考えないといけない。これはトレードオフなんです。どっちが絶対正しい、ってわけじゃない。
あと、レポート文化。さっきも言いましたけど、外資はレポートが英語だったり、すごくデータ重視だったりする。 それ、ちゃんと社内で評価されますか?っていう。社内の偉い人が「結局、新聞のこの記事が出たのが一番だ」って考えてるのに、Webのセンチメント分析の20枚のレポート見せても、「…で?」ってなっちゃうかもしれない。そういうカルチャーのすり合わせも、地味に大事です。

まとめ、というか…
まあ、そんな感じですかね。結局、日系か外資か、どっちが優れてるって話じゃないんですよね。自分たちの会社の状況とか、企業文化、あとはまあ…もちろん予算。それに、一番フィットするパートナーを見つける、っていう。ただ有名な外資系の名前を借りてきても、意味がない。
彼らが「どうやって」仕事をするのか、それが自分たちの「やり方」と合うのか。そこを、じっくり見極めるのが、一番大事なんじゃないかなって、思います。はい。
…と、ここまで話してみて、皆さんの経験もちょっと気になりました。PR会社(日系でも外資でも)と仕事したことありますか?もしあったら、一番「おっ」と思ったこととか、「これは違ったな…」みたいなこと、コメントで教えてもらえると嬉しいです。



