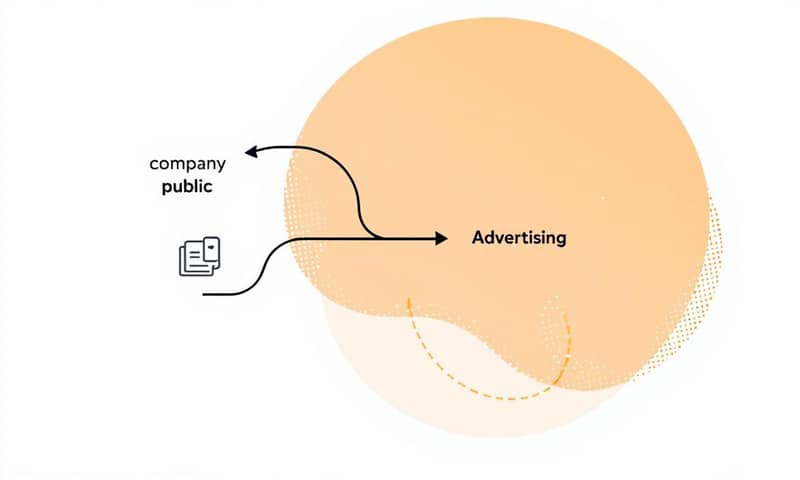PR会社について聞かれることが最近多い。たぶん、自社で情報を出すのが当たり前になったからだろうな。じゃあ、サクッとまとめてみるか。これは僕のメモみたいなものだけど、誰かの役に立てばいい。
先に結論だけ。PR会社って、結局なんなの?
一言でいうと、「企業と社会の”関係づくり”を代行してくれるプロ」。これに尽きる。商品を売る広告とはちょっと違う。もっと地味で、でも長期的に効いてくる活動。会社の「信頼」をじわじわ積み上げていく仕事、かな。ニュースに出たり、雑誌で紹介されたりするのは、その結果のひとつでしかない。そこを勘違いすると、うまくいかない。
よくある誤解:広告代理店と何が違う?
これは鉄板の質問。毎回聞かれる。一番の違いは、メディアの「枠」を買うか、買わないか。これだけ覚えておけばOK。
- 広告代理店:テレビCMや新聞広告の「枠」をバイイングする。お金を払って、確実に情報を載せる。短期的に認知を広げたいときに強い。
- PR会社:メディアに「面白いネタですよ」と情報を提供する。記者が「これは記事になる」と判断すれば、”編集記事”として無料で載る。 だから「パブリシティ」って呼ばれる。載る保証はないけど、第三者が書くから信頼性が高い。
要するに、広告は「お金で買う露出」、PRは「知恵で勝ち取る信頼」みたいな感じ。もちろん、最近はSNS運用とかイベント企画とか、両者の領域が被る部分も増えてるけどね。
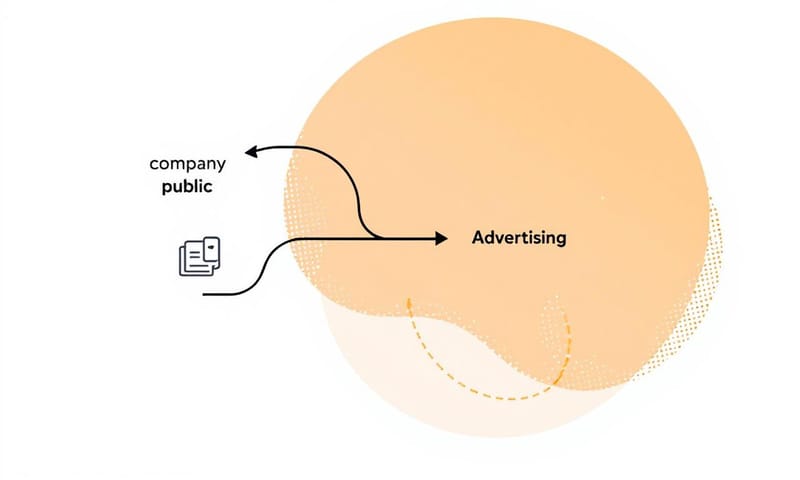
じゃあ、具体的に何をしてくれる人たち? [中の人の1日]
「メディアリレーションズ」とか言われても、ピンとこないよね。 実際のPR担当者の仕事って、かなり泥臭い。ちょっと覗いてみようか。
- 午前中:大量のニュースチェック。新聞、Webメディア、SNSを横断して、世の中のトレンドや競合の動きを把握する。自社が絡めそうなネタを探すのが目的。「あ、この社会問題とウチの技術、繋げられるかも」みたいな発想が大事。
- 昼:記者とランチ。これは大事な情報交換の場。最近どんなネタを探しているか、業界の裏話はどうか、みたいな雑談から企画のヒントが生まれる。関係づくりが命。
- 午後:プレスリリースの作成・配信。 ただ書くだけじゃない。「どのメディアの、どの記者に、どんな切り口で送れば響くか」を考えるのがプロの仕事。一斉送信は素人。
- 夕方:メディアへの電話フォロー。いわゆる「メディアプロモート」。リリースを送っただけじゃ読まれない。電話して「このネタ、面白くないですか?」と売り込む。ここで熱意とロジックが試される。
- 夜:クライアントへの報告書作成、明日の戦略立案。 掲載された記事のクリッピング、効果測定。そしてまた次の企画を考える。この繰り返し。
正直、地味な作業が多い。でも、この積み重ねが大きな成果に繋がるんだよな。
[海外との比較] 日本のPRとアメリカの「パブリック・アフェアーズ」
ここで少し視点を変えてみる。日本の「広報」って、主にメディア露出や商品PRが中心だよね。でも、アメリカとかだと「Public Affairs (PA)」っていう概念がもっと重要視される。 これは日本と大きく違う点。
- 日本の「広報 (PR)」:主な相手はメディアや消費者。マーケティング活動の一環として捉えられることが多い。
- アメリカの「Public Affairs (PA)」:主な相手は政府、行政、業界団体、NPOなど。政策提言やロビイング活動を通じて、自社に有利な事業環境を整えるのが目的。もっと経営戦略に近い。
もちろん、日本のPR会社が全くやらないわけじゃないけど、専門部署として強く機能しているのは外資系やグローバル企業に多い印象。これから日本企業も、こういう「社会のルール作りに参加する」視点でのPRが重要になってくると思う。ただニュースに出るだけじゃなくてね。

失敗しないための「PR会社の選び方」
じゃあ、どうやって良いパートナーを見つけるか。有名な会社が良いとは限らない。 大事なのは「自社との相性」。 下の表は、僕が会社を選ぶときにチェックする項目。単なる機能比較じゃなくて、「人」と「戦略」を見るのがポイント。
| チェック項目 | ダメな兆候(作業代行型) | 良い兆候(戦略パートナー型) |
|---|---|---|
| 実績の聞き方 | 「有名企業の実績がズラリ」。でも、具体的に何をしたかは曖昧。 | 自社の業界や規模に近い実績があるか。 「この課題を、この戦略で、こう解決した」とストーリーで語れる。 |
| 担当者の専門性 | 営業担当と実務担当が別。商談で「できます」と言ったことが、現場に伝わってない。 | 商談に出てきた人が、そのままメイン担当になる。 業界知識が豊富で、こちらのビジネスをすぐ理解してくれる。 |
| 戦略の提案 | 「とりあえずプレスリリースを10本打ちましょう」みたいに、手段から入る。 | 「御社の目的は〇〇なので、まずキーメッセージを固め、ターゲットメディアを絞りましょう」と、目的から逆算して提案してくれる。 |
| メディア人脈 | 「〇〇新聞と繋がりがあります」と言うだけ。具体性がない。 | 「〇〇新聞の△△記者は、最近こういうテーマに関心があるから、この切り口でアプローチできる」と、”顔が見える”関係性を持っている。 |
| 料金体系 | 料金表がシンプルすぎる。月額〇〇円で「活動一式」など、内訳が不透明。 | リテナー(月額固定)とプロジェクトベースの料金が明確。何にどれだけ工数がかかるか説明してくれる。 |
こんなはずじゃなかった…よくある失敗パターン
契約してから「なんか違う…」となるのは最悪。よくある失敗パターンを先に知っておこう。これ、本当に多いから。
- 報告が「掲載クリップ」だけ:月次レポートが、ただ掲載された記事のリスト。そこから「なぜ成功したか」「次はどうするか」という分析や提案がない。これはただの作業報告。
- 担当者がビジネスを理解しない:何度説明しても、業界の常識や自社の強みを分かってくれない。結果、的外れなプレスリリースやメディアアプローチを繰り返すことになる。
- 丸投げで社内にノウハウが貯まらない:PR会社に任せきりにして、社内の広報担当者が育たない。 契約が切れたら、またゼロからスタート。最悪のパターン。PRはあくまで伴走。社内にも担当者は必須。
- 「何でもやります」を信じてしまう:戦略PR、SNS、イベント、危機管理…全部「できます」という会社は、逆に注意。本当に全部のレベルが高い会社は稀。得意領域を見極めることが大事。
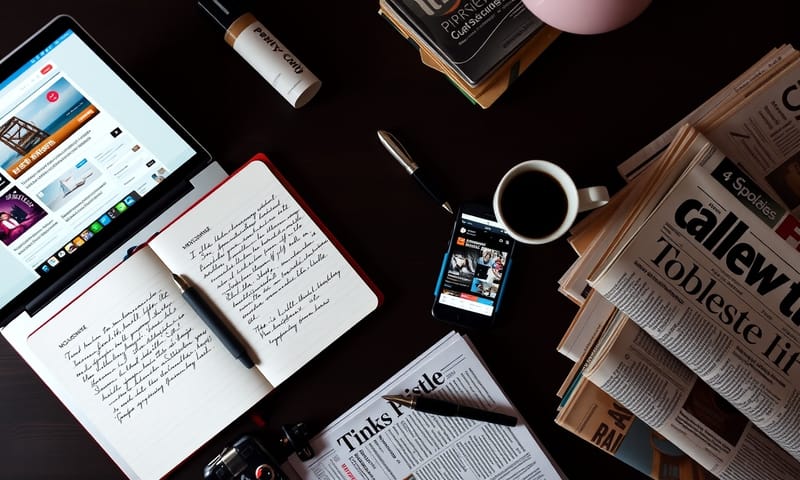
費用って、ぶっちゃけどれくらい?
一番気になるお金の話。これは本当にピンキリ。会社の規模や依頼内容によるから、あくまで目安として聞いてほしい。
- リテナー契約:月額固定で、継続的にコンサルティングやメディアリレーションズをお願いするパターン。中堅〜大手のPR会社だと、安くても月額50万〜100万円くらいからが相場かな。 年間契約が基本。
- プロジェクト契約:新商品発表会や記者会見など、単発のイベントごとにお願いするパターン。規模によるけど、数十万〜数百万円。
- 成果報酬型:テレビで〇分紹介されたら〇〇円、みたいな契約。一見お得に見えるけど、戦略的な動きより短期的な露出獲得に偏りがちなので、個人的にはあまりお勧めしない。
安いから、という理由でフリーランスや小規模な会社に頼むのも手だけど、その場合は「できること」と「できないこと」の見極めがさらにシビアになる。結局、何を目的に、どこまでのサポートを求めるか次第だね。
さて、ざっと書いたけど、PR会社について少しは解像度が上がっただろうか。大事なのは、PR会社を「魔法使い」だと思わないこと。彼らはあくまでパートナー。自社の魅力を棚卸しして、社会と繋がるための戦略を一緒に考えてくれる存在だ。だからこそ、選ぶときは慎重に、ね。
あなたの会社がPRで達成したいことは何ですか?
もしPR会社に依頼するなら、一番に何を達成したいですか? 「認知度向上」「ブランディング」「採用強化」など、あなたの考えをぜひコメントで教えてください。