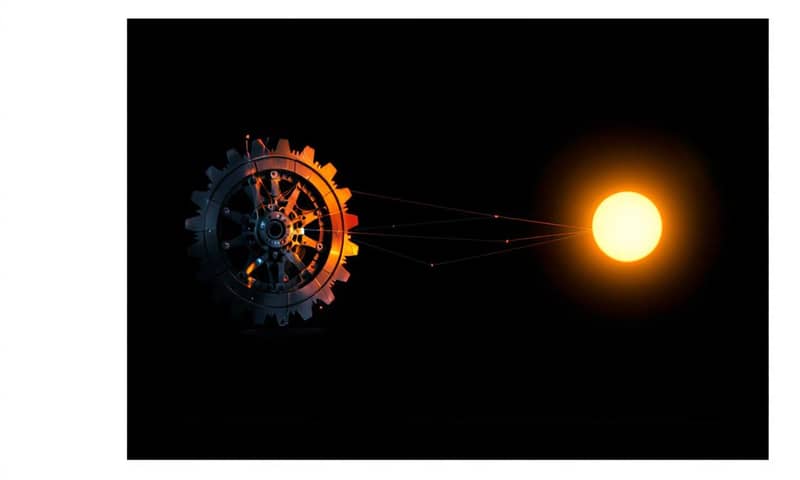なんか最近、よく聞かれるんだよね。「広報ってどんな人が向いてるんですか?」って。うーん…これ、答えるの結構むずかしい。🤔
正直、キラキラしたイメージを持たれがちだけど、現実はかなり地味な作業も多いし…。 でも、だからこそ面白い部分もあるんだけどね。
いきなり結論から言うと…
まあ、一言でいうなら「会社の翻訳家」みたいな人かなって思う。専門的で硬い社内の言葉を、世の中の人が「なるほど」って思える言葉や物語に変換していく仕事。そんな感じ。
あとは、会社やサービスの「一番のファン」でありながら、同時に一番冷静な「批評家」でいられる人。このバランス感覚が、たぶん一番大事。
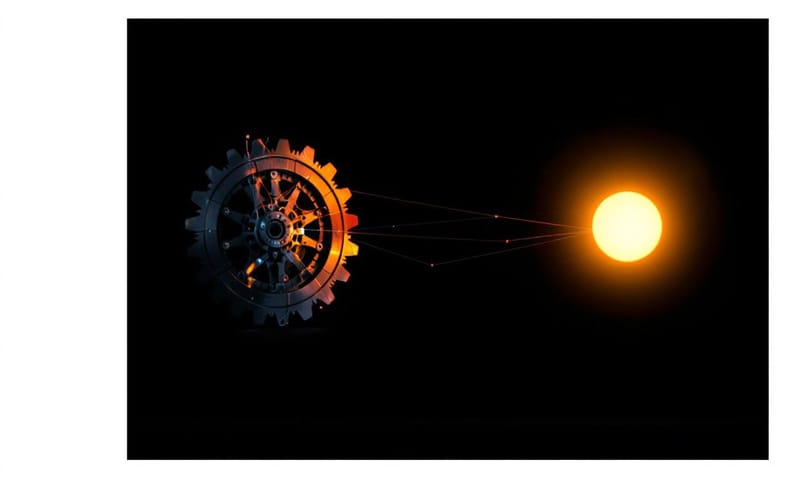
じゃあ、求められるスキルって具体的に何?
よく「コミュニケーション能力」とか「文章力」って言われるけど、それだけだとちょっと足りないかな。 もう少し、広報の仕事に特化して考えてみると、個人的にはこの5つが大事だと思う。
- 翻訳・言語化スキル: これはただ文章がうまいとかじゃなくて、技術者が話す専門用語や、経営陣の難しいビジョンを、中学生でもわかるような言葉に「翻訳」する力。プレスリリースを書くのも、SNSで発信するのも、全部このスキルが基本になる。
- 俯瞰力と当事者意識のバランス: 会社全体を鳥の目で見て「今、社会に対して何を言うべきか」を考える冷静さ。 と同時に、一つのプロジェクトに対して「これは自分がやるんだ」っていう熱量。この両方を行ったり来たりできる人が強い。 '
- しなやかなストレス耐性: 広報って、たまに会社の「矢面に立つ」仕事でもあるんだよね。 特に炎上した時とか…。ただ頑丈なだけじゃなくて、批判をちゃんと受け止めて、次に活かせるような、柳みたいな「しなやかさ」が要る。正直、これが一番キツいかも。😅
- 好奇心と情報収集力: 世の中のトレンドはもちろん、競合の動き、自社の各部署が今何に困っているか…とか、常にアンテナを張っておく必要がある。 「これ、何でだろう?」って思う好奇心が全ての始まり。
- 誠実な調整・交渉力: 社内のいろんな部署と「これを出す・出さない」の調整をしたり、メディアの人と「こういう企画どうですか?」って交渉したり。 人と人の間に立つ仕事だから、相手へのリスペクトと誠実さが無いと、結局うまくいかないんだよね。

【自己診断】向いてる人 vs そうでもないかも…な人
ちょっとした適性診断みたいなもの。どっちが良い悪いじゃなくて、単に「どっちのタイプがよりストレスなく働けるか」って話。
| こういう人、向いてるかも | こういう人は、ちょっと大変かも |
|---|---|
| 「なんで?」って思うことが多い人。知的好奇心ってやつかな。😌 | 自分の意見ややり方が絶対!ってなっちゃう人。調整が多いからね…。 |
| 人の話を聞くのが割と好きな人。取材とかヒアリングが基本だから。 | 注目されるのは好きだけど、地味な作業は苦手な人。資料作成とか多いよ。 |
| 物事を客観的に見れる…でも冷めてるわけじゃない人。 | 白黒ハッキリつけないと気が済まない人。広報の答えはグレーなことも多い。 |
| 縁の下の力持ち的な役割に喜びを感じる人。主役はあくまで会社やサービス。 | 短期的な成果をすぐ求めちゃう人。広報は長期戦だから…。 |
日本の広報、ちょっと特殊かも?
そういえば、海外と日本の広報って、メディアとの付き合い方が少し違うんだよね。特に「記者クラブ」っていう日本独特の仕組み。
これは官公庁とか大きな組織に置かれている記者さんたちの詰所みたいなもので、ここに加盟してると情報が取りやすい。 メリットもあるんだけど、一方で、クラブに入れないフリーランスや海外メディアは大事な情報にアクセスしにくいっていう問題も指摘されてる。 アメリカとかだと、もっとオープンにいろんなメディアが直接企業にアプローチする感じが強いかな。 だから、日本でメディアリレーションズをやるなら、この独特の文化を理解しておくのは結構大事。
よく聞かれること
最後に、よくある質問にいくつか答えておこうかな。
- 未経験でもなれますか?
なれると思う。実際、営業とかマーケティング、人事とか、別の職種から来る人も多い。 大事なのは、その会社や業界への興味と、さっき挙げたようなスキルを意識して行動できるかどうか。 - 有利な資格ってありますか?
「PRプランナー」っていう資格はあるけど、必須じゃないかな。 それよりも、実際に文章を書いたり、何かの企画を立てて人を動かした経験の方がよっぽどアピールになると思う。 - ぶっちゃけ、大変ですか?
うん、大変な時はすごく大変。笑 でも、自分たちが仕掛けたことで、世の中の反応がパッと変わる瞬間とか、今まで知られてなかった魅力が広まっていくのを見ると、全部吹き飛ぶくらい嬉しいよ。これホント。😌
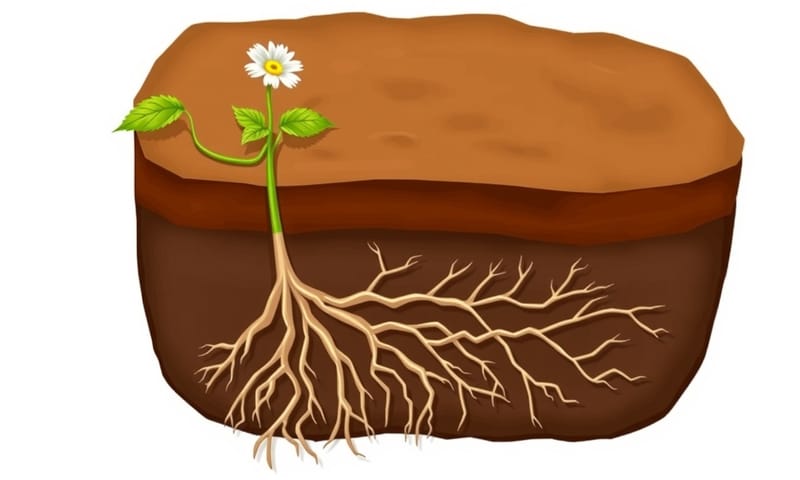
…と、まあ、つらつらと書いてみたけど、結局は「自分が仕える会社やサービスを、心から世の中に広めたいと思えるか」に尽きるのかもしれない。その気持ちがあれば、スキルは後からついてくるはず。
ちなみに、あなたが思う「広報が上手いな〜」って企業、どこかありますか? もしよかったら、理由と一緒に教えてくれると嬉しいな。参考にしたいので。✍️