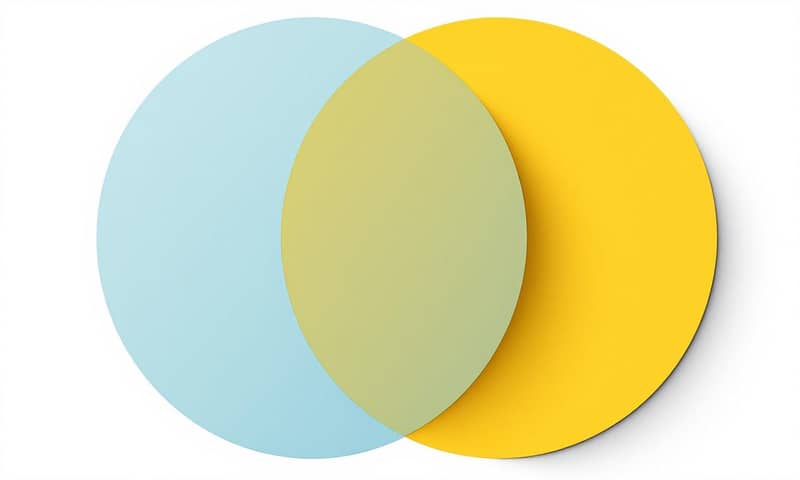最近、広報って結局なんなんだろうって、ふと考えることがあるんです。プレスリリースを出すこと?メディアの取材対応?…もちろんそれも大事な仕事の一部。でも、それだけじゃない。正直、もっと泥臭くて、地味な作業の積み重ねなんですよね。
昔、ある小さな会社で広報を始めたばかりの人が「何から手をつけていいか…」と途方に暮れていたのを思い出します。 その気持ち、すごくわかる。情報が社内のあちこちに点在してて、それを繋ぎ合わせるだけでもう大変。だから、ただ情報を外に出すだけじゃなくて、社内の情報を「翻訳」して、社会がわかる言葉に変換する作業。それが広報の本質なんじゃないかなって。
一言でいうと、広報は「社内外の翻訳家」
そう、結局これに尽きる気がします。開発チームの専門用語だらけの仕様書を、読んだ人が「へぇ、面白そう」って思えるような言葉に翻訳する。経営陣の熱いビジョンを、社員みんなが「なるほど、自分たちの仕事はここに繋がるのか」と納得できる言葉に翻訳する。 この「翻訳」の精度が、会社の印象を良くも悪くも左右する。だから、すごく責任重大な仕事なんですよね。
じゃあ、具体的に何するの?タスクを分解してみた
「翻訳家」と言っても、やることは本当に多岐にわたります。 大きく分けると、会社の外に向かう「社外広報」、中に向かう「社内広報」、そして何かあった時のための「危機管理広報」の3つでしょうか。
- 社外広報: これが一番イメージしやすいやつですね。新商品や新しい取り組みを世の中に知らせる活動。プレスリリースの作成・配信、メディア関係者とのリレーション構築、イベントの企画・運営、SNSでの発信など。
- 社内広報: 意外と見落とされがちだけど、実はめちゃくちゃ重要なのがこれ。社内報を作ったり、社内イベントを企画したりして、会社の方向性や他の部署の動きを社員に伝える役割です。 これがうまくいってないと、社員がバラバラの方向を向いちゃう。
- 危機管理広報: 守りの広報。製品の不具合や不祥事など、ネガティブな事態が発生した時に、いかにダメージを最小限に抑えるか。情報の整理、対外的な説明、社内への状況共有など、冷静な判断が求められます。
最近の調査だと、上場企業は特に株主や顧客、個人投資家といった「個」を重視する傾向が強まっているみたいです。 つまり、ただ広く知らせるだけじゃなくて、「誰に」「何を」伝えるかをより戦略的に考えないといけない時代になってるってことですね。
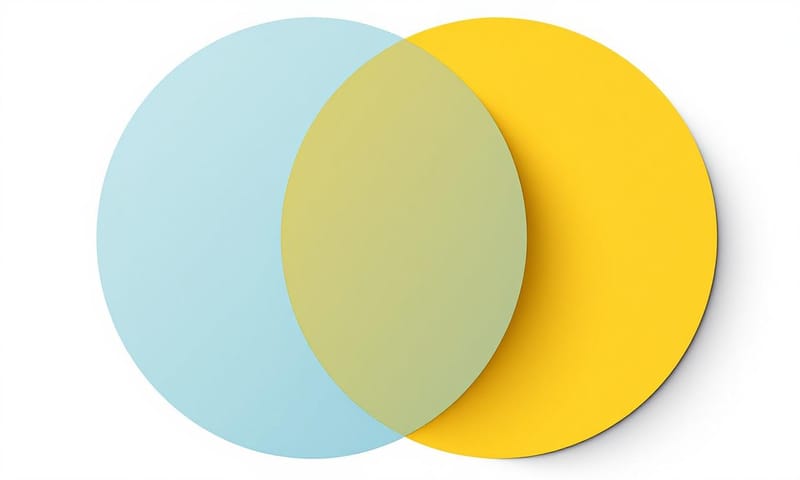
これらのタスクを、もう少し「攻め」と「守り」という観点で整理してみると、頭が整理しやすいかもしれません。
| 広報のタイプ | 目的 | 具体的なタスク例 | 個人的な感想 |
|---|---|---|---|
| 攻めの広報 (Proactive PR) | 認知度向上、ブランドイメージ構築、ファン作り |
|
こっちは企画を考えるのが楽しい。ゼロからストーリーを作って、それが世の中に広まっていくのを見ると、やっぱり嬉しいですよね。クリエイティブな側面が強いかな。 |
| 守りの広報 (Reactive PR) | レピュテーションの維持・回復、リスクの最小化 |
|
正直、こっちは精神的にかなり削られます…。でも、ここでどう対応するかで会社の真価が問われる。スピードと誠実さが何よりも大事。地味だけど、会社の土台を守る重要な仕事。 |
現場のリアルな業務フロー:ある新機能リリースの一週間
じゃあ、実際の現場ってどんな感じで動いてるの?っていうのが一番気になるところだと思います。 例えば、あるアプリの新機能がリリースされるまでの一週間を想像してみましょう。これはあくまで一例ですけど。
- 月曜日:キックオフと情報整理
まず、開発、マーケ、営業など、関係部署の担当者を集めてミーティング。「この機能の『売り』はどこ?」「誰に一番使ってほしい?」「技術的に新しい点は?」といった情報を徹底的にヒアリングします。ここで得た情報が、プレスリリースの骨子になる。このすり合わせが一番大事で、ここで間違うと全部がズレます。 - 火曜日:原稿作成と承認フロー
ヒアリングした内容をもとに、プレスリリースのドラフトを作成。専門用語を避け、誰が読んでもわかる言葉で書くのがポイント。 そして、ここからが長い…各部署の責任者、法務、そして役員と、承認を得るための長い旅が始まります。朱字がどんどん入って、原型がなくなることも…。 - 水曜日:メディアリストの作成と配信準備
承認された原稿を元に、配信準備。どのメディアに送るか、メディアリストを精査します。ただ闇雲に送っても読まれないので、「この記者さんはこの分野に詳しそうだな」とか、過去の記事を読みながら一人ひとり選んでいく地道な作業。 - 木曜日:プレスリリース配信と個別ピッチ
午前10時~11時くらいが狙い目かな…。配信サービスを使って一斉に配信。でも、これで終わりじゃない。特に取り上げてほしい重要なメディアの記者さんには、個別に電話やメールで「実はこういう背景がありまして…」と補足説明をします(メディアキャラバンとも言いますね)。 ここで関係性が生きてくる。 - 金曜日:掲載モニタリングと効果測定
朝からネットニュースやSNSをひたすらチェック。「クリッピング」と呼ばれる作業です。 記事にしてくれたメディアがあれば、すぐ社内に共有。SNSでどんな反響があるか、ユーザーの声を拾うのも大事な仕事。そして、これらの結果をまとめて、週明けの報告会に備えます。
ツールはどれ使う?目的別の選び方
これだけの業務を全部手作業でやるのは、正直無理です。なので、みんな何かしらのツールを使っています。 目的別にいくつか紹介しますね。
- プレスリリース配信:これはもう定番。日本では「PR TIMES」が圧倒的に強いですが、「共同通信PRワイヤー」なども大手です。 配信するだけでなく、どのくらい読まれたか分析できる機能もあったりします。
- メディアモニタリング:新聞、雑誌、Webニュース、SNSでの自社に関する言及を自動で集めてくれるツール。「PR Analyzer」や「Meltwater」などが有名です。 これでエゴサーチの手間がかなり省けます。
- 社内情報共有:社内報をWebで簡単に作れるツールや、情報共有をスムーズにするためのビジネスチャットツールなど。これは会社によって様々ですね。
ここで少し面白いのが、海外のツールと日本のツールの違い。例えば、グローバルで強い「Meltwater」は、SNS分析や海外メディアのカバレッジは本当にすごい。 でも、日本の地方紙や業界専門誌まで細かく追いたい、となると、国内のサービスの方が強かったりします。 例えば「日経スマートクリップ」は新聞記事に特化していて、紙面のレイアウトそのままに見れるのが便利だったり。 結局、何を一番重視するかで選ぶツールは変わってきます。海外展開を考えるならMeltwaterのようなグローバルツールは心強いし、国内のBtoBが主戦場なら国内特化のツールの方が費用対効果がいいかもしれない。

でも、これだけじゃうまくいかない:広報の「落とし穴」
ここまで色々とタスクやツールを紹介してきましたが、正直、これを全部やってもうまくいかない時があります。いくつか、広報初心者がハマりがちな「落とし穴」があって…。
- プレスリリース投げっぱなし病:配信して満足しちゃうパターン。 配信はスタートでしかなくて、その後の個別フォローや関係構築がなければ、記事になる確率はぐっと下がります。
- 社内調整の軽視:外ばかり見て、社内の協力を得るのを怠ってしまうこと。 結局、情報を持っているのは現場の社員。彼らとの信頼関係がないと、良いネタは出てきません。最近の調査でも、広報立ち上げ期の担当者は「社内の合意・協力」に課題を感じている人が多いようです。
- 「効果測定=掲載数」という勘違い:「今月は10件掲載されました!」と報告しても、経営層からすると「で、それが売上にどう繋がったの?」で終わってしまう。 掲載数だけでなく、その記事がどんな影響を与えたのか、サイトへのアクセスは増えたのか、問い合わせに繋がったのか、というところまで見ないと、活動の価値が伝わりません。
- 経営との目線ズレ:これは結構深刻な問題。広報は「会社の認知度を上げたい」と思っていても、経営者は「事業に貢献してほしい」と思っている。このズレがあると、どんなに頑張っても評価されにくい。日本広報学会の調査でも、経営者は広報担当者に専門知識以上に「ビジネスパーソンとしての広い視座」を求めている、という結果が出ています。
結局、広報の仕事って、メディアや社会との関係構築であると同時に、社内や経営陣との関係構築でもあるんですよね。両方のバランスが取れていないと、車輪がうまく回らない感じです。

色々話してきましたが、広報の仕事は本当に奥が深くて、これという正解がないのが面白いところでもあり、難しいところでもあります。ただ一つ言えるのは、会社と社会を繋ぐ、めちゃくちゃやりがいのある仕事だということです。
これを読んでいるあなたは、広報のどんな仕事に一番興味を持ちましたか?もしあなたが広報担当者なら、一番時間のかかるタスクは何ですか?ぜひ、ご意見聞かせてください。