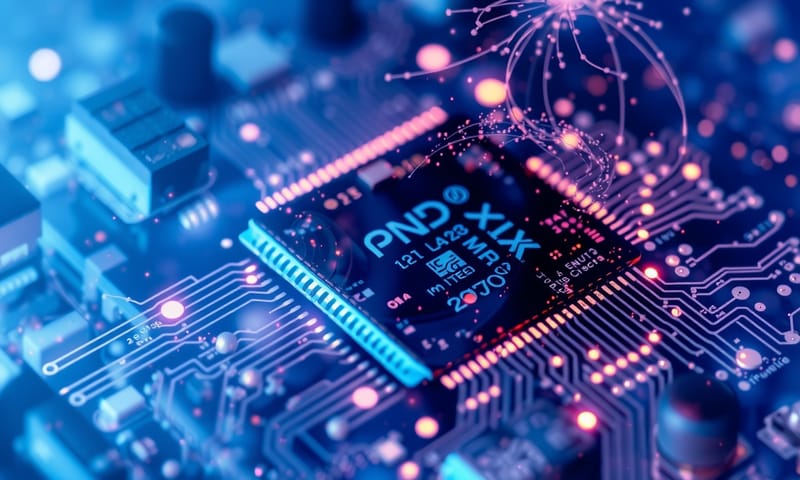重点一句話
これまでのIoTって、正直ちょっと「だから何?」って感じだったけど…ようやく本当に空気が読める、賢いものに進化し始めた。そういう話。
「昔のスマート」と「今のスマート」
思い出せる? 一昔前のIoTブーム。コーヒーメーカーにWi-Fiがついたり、スマホで照明をつけたり消したり…。で、そのスマホをどこに置いたか忘れる、みたいな。
あれはあれで面白かったけど、正直「ガジェットの寄せ集め」だったと思う。スマート照明とスマートスピーカーがうまく連携してくれない。新しい機器を追加するたびに、設定地獄が待ってる。結局、一個一個のデバイスをスマホアプリで操作するだけで、生活が「賢く」なったかっていうと、うーん…
コンサル会社のMcKinseyのレポート[2021年]でも言ってたけど、多くの企業がPoC(実証実験)から抜け出せてなかったらしい。単にトースターにアプリをつけただけじゃ、朝食に革命は起きないってことだね。

でも、最近の流れは全然違う。アンビエント・インテリジェンス [Ambient Intelligence] とか言われてるけど、要はデバイス単体じゃなくて、「環境」全体が賢くなるイメージ。
例えば、仕事から疲れて帰ってくる。家がそれを察知して、照明を暖色系の落ち着いた明るさに落としてくれる。エアコンがちょうどいい温度に調整して、静かな音楽を流し始める。こっちが何も言わなくても、全部「察して」くれる感じ。これはもう、ただの遠隔操作じゃない。
これが「今のスマート」。デバイス同士が裏側で勝手に会話して、ユーザーが一番快適な状態を作り出す。まるで、すごく気の利く執事がいるみたいに。
じゃあ、どうやって実現してるの?
この「気の利く環境」を作るために、いくつかの技術がパズルのピースみたいに組み合わさってる。正直、この裏側の仕組みが一番面白いところ。
昔のIoTと今のAIoT [Artificial Intelligence of Things] を比べると、たぶん分かりやすい。
| 要素 | 昔のIoT(ガジェットの寄せ集め) | 今のAIoT(賢い環境) |
|---|---|---|
| 接続性 | 個別にWi-Fi接続。ルーターの負担がすごい。設定も面倒。 | Wi-Fi, BLE, Zigbee…適材適所。デバイス同士が会話する感じ。 |
| 知能 | スマホアプリ頼り。結局は人間が指示しないと動かない。 | エッジとクラウドで自律的に判断。「たぶんこうして欲しいだろう」を予測する。 |
| データ | ただ集めるだけ。せいぜいグラフで可視化するくらい。 | パターンを学習して、次の行動を最適化するために使う。データが燃料になる。 |
| 体験 | 設定が面倒。よく接続が切れる。「使うぞ」と意識する必要がある。 | 意識しない。そこに「ある」のが当たり前。空気みたいになるのが理想。 |
この表にあるみたいに、接続方法、知能の置き場所、データの扱い方…全部が変わってきてる。
裏を支える技術たち [ちょっとだけ専門的な話]
神経網としてのネットワーク
まず、すべてのデバイスを繋ぐネットワーク。これが人間の神経系みたいなもの。これが貧弱だと、賢い体も動かない。
- WiFi: みんな知ってるやつ。速いけど、消費電力が大きくて、デバイスが増えすぎると詰まる。
- Bluetooth/BLE: イヤホンとかでお馴染み。近距離専門。ウェアラブルデバイスには必須。
- Zigbee/Z-Wave: スマートホームの本命かも。家みたいな狭い範囲で、機器同士が直接バケツリレーみたいに通信する [メッシュネットワーク]。ルーターの負担が少ない。
- LPWANs: めっちゃ省電力で、めっちゃ遠くまで届く。スマート農業で畑のセンサーからデータを送るとか、そういう用途。牛にもコネクティビティを、ってやつ。
どれか一つじゃなくて、これらを組み合わせるのが今の主流。

反射神経としてのエッジコンピューティング
次に大事なのが、賢さを「現場」に置くっていう考え方。エッジコンピューティングのこと。
昔は、センサーが取得したデータを全部インターネットの向こう側にあるクラウドに送って、そこで判断して、指示を返してた。これだと、どうしてもタイムラグが生まれる。それに、通信量もバカにならない。
だから、デバイスの側、つまり「エッジ」でできる判断は、その場でやっちゃおう、と。例えば、防犯カメラが「人」を検知したとき、それが家族なのか不審者なのかをカメラ自体がある程度判断する。本当にヤバいときだけクラウドに知らせる。これなら反応も速いし、プライバシー的にもちょっと安心。
司令塔としてのクラウド
じゃあクラウドが要らなくなったかというと、全然そんなことはない。むしろ逆。クラウドは全体の「脳」として、もっと高度な仕事をするようになった。
エッジから送られてくる選りすぐりのデータを大量に蓄積して、分析する。例えば、「この家の人、毎週金曜の夜は照明を暗くしてジャズを聴いてるな」みたいなパターンを見つけ出す [パターン認識]。あるいは、工場の機械の振動データを分析して「このモーター、来週あたり壊れるかも」って予測したり [予知保全]。
2025年には世界中のIoTデバイスが生み出すデータ量が79.4ゼタバイト…とかいう、もう想像もつかない数字になるらしい [IDC調べ]。これを個人や一企業レベルで捌くのは不可能。こういう膨大なデータを処理して「知性」を生み出すのが、クラウドの役割。