はい、どうも。えーっと、今日は「会社の広報」について話してほしいっていうリクエストがあったので、ちょっと僕なりに解説してみようかなと思います。よく「広報って何やってるの?」って聞かれるんですけど、一言で言うのはなかなか難しいんですよね。まあ、でも、やっていきましょう。
一言で言うと、広報って何?
いきなり結論から言っちゃうと、広報っていうのは、単に「お知らせ」をする仕事じゃないんですよ。そうじゃなくて、「会社と社会との間で、良い関係を築くための全てのコミュニケーション活動」だと僕は思ってます。これには、会社が良い時だけじゃなくて、悪い時、つまり不祥事とかがあった時の対応も含まれます。信頼関係を築いて、それを維持していく、すごく地道な仕事ですね。
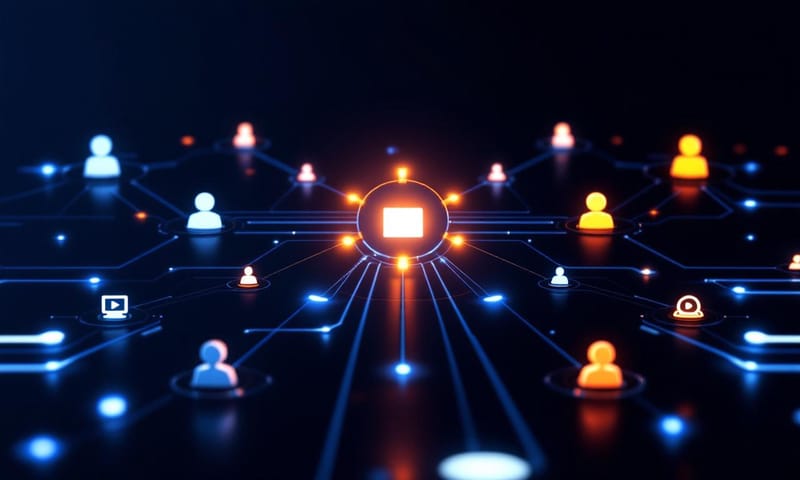
具体的にどんな仕事があるの?
じゃあ、具体的に何をするのか。まあ、いろいろありますけど、代表的なものをいくつか挙げてみますね。
- メディアリレーションズ: これが多分、一番イメージしやすいやつですね。新聞、雑誌、テレビ、そして今やWebメディアの記者さんたちと関係を作って、会社のことを記事にしてもらう活動です。 ただ、昔みたいにプレスリリースを投げて終わり、じゃないんですよ。今は、記者さんの興味関心とか、世の中のトレンドをちゃんとこっちが理解して、「この記事、〇〇さんだったら興味あるんじゃないですか?」って提案する感じ。こっちから仕掛けていく姿勢が大事なんです。
- プレスリリースの作成・配信: 新商品とか、新しい取り組みとか、会社のニュースを文章にして発表すること。 これもただ書けばいいわけじゃなくて、どういうタイトルだと記者の目に留まるか、どういう切り口だとニュースとして価値が上がるかを考え抜いて作ります。最近だと「PR TIMES」みたいな配信サービスを使うのが一般的ですね。
- 危機管理対応(クライシス・コミュニケーション): これ、めちゃくちゃ重要です。製品の不具合とか、社員の不祥事とか、会社にとってネガティブなことが起きた時に、どうやって情報を開示して、どう謝罪して、どう信頼を回復していくかを設計する仕事。 ここでの対応を間違えると、会社の存続に関わることもありますからね…。本当に神経を使います。
- 社内広報: 意外と見過ごされがちだけど、すごく大事なのがこれ。 社員に向けて、会社の方向性とか、他の部署の頑張りとかを伝える役割です。社内報を作ったり、社長のメッセージを発信したり。 社員が自分の会社に誇りを持てないと、良い製品やサービスなんて作れないですからね。従業員のモチベーション向上にも繋がります。
- SNSやオウンドメディアの運営: 最近はもう当たり前になりましたけど、会社の公式Twitter(現X)とか、ブログとかを運営するのも広報の仕事であることが多いです。 ここは、お客さんと直接コミュニケーションが取れる貴重な場所なので、炎上しないように気をつけながらも、会社の「中の人」の体温が伝わるような発信を心がけます。
社内広報と社外広報、何が違う?
さっき社内広報の話が出ましたけど、広報は大きく「社外向け」と「社内向け」に分けられます。 どっちも重要なんですけど、目的とかやり方がちょっと違うんですよね。簡単に表にしてみました。
| 社外広報 | 社内広報 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | お客さん、メディア、株主、取引先、地域社会など、会社の外にいるすべての人たち。 | 社員、そしてその家族。意外とこれが難しいんですよ、身内だからこそ。 |
| 主な目的 | 会社の認知度やブランドイメージを上げること。 最終的には製品を買ってもらったり、ファンになってもらったり。 | 会社のビジョンや戦略を共有して、社員の一体感を高めること。 「この会社で働いててよかった」って思ってもらうのがゴール。 |
| 使うツール | プレスリリース、記者会見、SNS、広告、イベントなど。外の世界に向けたあらゆる手段。 | 社内報、イントラネット(社内Webサイト)、社長からのビデオメッセージ、社内イベントとか。結構クローズドな世界。 |
| 難しさ | 情報が多すぎて、そもそも見てもらえない。どうやって他社より目立つか、常に考えないといけない。 | 「どうせ会社の宣伝でしょ」って社員にスルーされがち。身内だからこその冷めた目線をどう乗り越えるかが鍵。 |

日本と海外の広報の違いって?
これ、結構面白いポイントなんですけど、日本の広報と、例えばアメリカの広報って、やり方が全然違う部分があるんですよ。 一番大きいのは、メディアとの付き合い方かな。
日本には「記者クラブ」っていう、ちょっと独特な仕組みがありますよね。官公庁とか大きな業界団体の中にあって、そこに加盟してるメディアの記者さんが常駐してる。だから、何か発表がある時は、まず記者クラブで説明会を開く、みたいなのが伝統的なやり方でした。これはこれで、一度にたくさんの主要メディアに情報を伝えられるメリットはあります。
一方、アメリカとかだと、そういう記者クラブはあまり一般的じゃない。 じゃあどうするかというと、広報担当者が自分でメディアリストを作って、一社一社、一人一人の記者に直接メールとか電話で売り込み(ピッチ)をかけるのが基本なんです。 「あなたのこの記事を読んだけど、うちの会社のこの技術は、その続報として面白いと思いませんか?」みたいに、かなりパーソナルなアプローチをします。 日本だと、配信後に電話でフォローするのは嫌がられることもありますけどね。 だから、海外で広報をやるなら、現地の文化とか商習慣をしっかり理解しないと、全然相手にされないってことですね。
広報に求められるスキルは?
じゃあ、どんな人が広報に向いてるのか、どんなスキルが必要なのか。これもよく聞かれます。コミュニケーション能力はもちろん大事なんですけど、それだけじゃないんですよね。
- 文章力: プレスリリースとか、SNSの投稿とか、とにかく「書く」ことが多い。 会社の顔として出す文章なので、分かりやすくて、かつ魅力的な文章を書ける力は必須です。
- 情報収集・分析力: 世の中のトレンド、競合の動き、自社がどう見られてるか…。常にアンテナを張って情報を集めて、それを分析して次の戦略に活かす力が必要です。
- 企画力: ただ情報を流すだけじゃなくて、「どうやったら面白く伝わるか」を考える力。 時にはイベントを企画したり、意外な会社とコラボしたり、そういうクリエイティブな発想が求められます。
- 関係構築能力: まあ、いわゆるコミュ力ですけど、特にメディアの人たちと長期的に良い関係を築く力は大事ですね。 一方的な情報提供じゃなくて、相手にとっても有益な情報源になることが信頼につながります。
- 危機管理スキル: これはもう、冷静さと胆力。パニックにならずに、何が起きていて、何をすべきかを整理して、経営陣に進言できる力。これは経験がモノを言いますね。
- データ分析力: 最近は特にこれ。 出した記事がどれくらい読まれたか、SNSでどれくらい反響があったか、ちゃんとデータを分析して「なぜ成功したのか」「次はどう改善するか」を考えられないと、プロとは言えません。
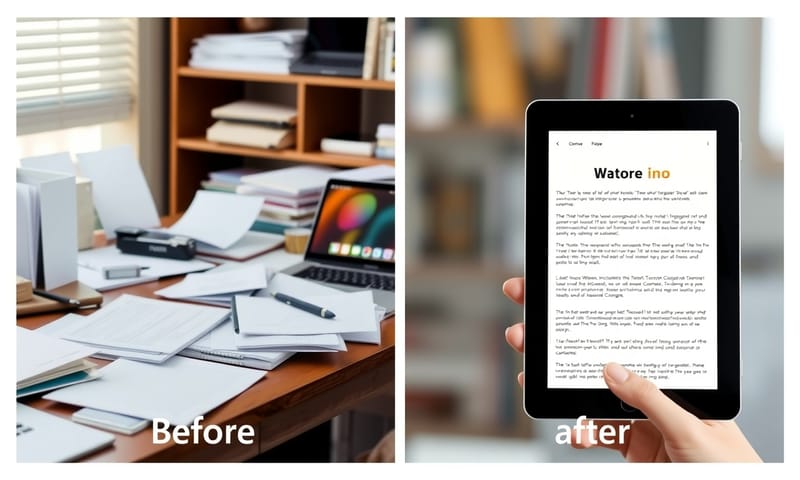
じゃあ、広報のやりがいは?
大変なことも多い仕事ですけど、やっぱりやりがいは大きいですよ。一番は、自分たちが仕掛けた情報発信で、世の中の反応が目に見えた時ですかね。 商品がすごく売れたとか、SNSでトレンド入りしたとか。そういう時は「やった!」って思います。
あと、個人的には、会社のブランド価値向上に貢献できることかな。 広報活動を通して、社会から「あの会社って、いいよね」って思ってもらえるようになったり、社員が「自分の会社、好きだな」って言ってくれたり。 そういう瞬間は、地道にやってて良かったなあって、心から思いますね。企業の成長を内側から支えている実感があります。
最近だと、ESG経営、つまり環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視する経営が注目されてますけど、こういう会社の姿勢を社会に正しく伝えていくのも、まさに広報の重要な役割になってきています。 こういう活動を通じて、間接的に社会貢献ができるのも、やりがいの一つかもしれません。
これから広報を目指す人へ
えー、だいぶ長々と話しちゃいましたけど、なんとなく広報の仕事、イメージ湧きましたかね。情報を作って、届けて、関係を築く。すごく奥が深くて、面白い仕事だと思います。
もしあなたがこれから広報の仕事に興味があるなら、どの部分に一番ワクワクしますか?戦略を練る部分ですか?それとも、クリエイティブなコンテンツを作る部分?あるいは、人と会って関係を築いていくところでしょうか。よかったら、コメントで教えてもらえると嬉しいです。



