ここから始めよう - アルゴリズム時代のSNSで多様性と個性を守るための実践ヒント
- 週1回、自分がフォローしていないジャンルや国のアカウントを新たに2つ追加する
情報源の幅が広がり、アルゴリズムによる偏りを減らせるから
- 毎月一度、投稿やリアクション内容を見直し“本音”で発信できているか自問する
個性や多様性への感度が鈍らず、共感できる仲間とも出会いやすくなる
- 気になる話題は必ず3人以上異なる意見・立場から確認してみる
思い込みやアルゴリズムによる情報バイアスに気付きやすくなる
- "いいね"だけでなくコメント・シェアも月5回以上積極的に行う
参加型文化に触れることで多様な価値観と交流し視野が広げられる
ソーシャルメディアのアルゴリズムと視聴体験の違いを知る
ソーシャルメディアのアルゴリズム、その扱い方について騒がれているけど……本当にデータ集めの倫理とか、新しい仕組みによるプラットフォーム全体の「なんとなく違う」感じ、もっとしっかり考え直したほうが良くないかな。いや、この種の話自体、そんな目新しいものじゃない気もするんだけど。うん、「3秒ルール」だとか、あとまあ腹立たせる動画──rage baitってやつ?──みたいな手法は昔からちょっと工夫変えて何度も繰り返されていて、本質的にはそこまで大きな落とし穴でもなかったと思う。でもさあ、それこそテレビでも同じような現象はよく見られたでしょう。チャンネル変えさせないために必死で構成してたり。「そうはいっても」、あの頃はリモコン片手に次どこへ移るかちゃんとわかってて、不意になんとなく戻りたい時も、割と簡単に元通りになるっていう安心感が確かにあった。映像コンテンツ全体が整理されていて数にも限度があり、「次はこれ」という選択権はぼんやりしながらも握れていたっぽい。しかし今となれば、と言いたいところだけど、ユーザー側で観る内容を厳密に決定できなくなったという実感がついてまわるようになった。この現状、大量無尽蔵とも思える動画群から「次」に進む基準や道筋までもアルゴリズム頼みになっちゃってさ、なんだろうね、不意に自由を取られてしまった錯覚すらある。ま、いいか。
現代アルゴリズムが与えるコンテンツ消費の不自由さを理解する
どこかでリストをスクロールして探すなんてことはもうなくなってしまった、という感覚が正直あるんだよね。見えない規則でコンテンツが次から次へと供給されるのに、実際には自分が同じ映像に戻ろうとしても無理だったり、昔お気に入りだった作り手のページも二度とたどり着けなかったりする。この不可視の構造…コンテンツたちは、限りない情報の波間にまぎれて消えてしまう。「ほんとう、不思議だよ」とふと思う。気づいたら競争ばかりは依然として終わっていなくて──でも、自分自身、いま何というシステム相手に足掻いているのか、それとも乗っかろうとしているだけなのかも定かじゃなくなる。この奇妙さはね、過去によく言われてきた議論がふと頭をよぎる時と似てる。「本当に一つ年上だからって別世代を非難する資格が誰にあるんだろ」、みたいな曖昧な違和感とか。注意力が持続しないとかさ、「過剰消費」の話題になった瞬間とか、それからアルゴリズム云々による政治操作を巡って盛り上がるときもあったっけ。でも……どうにも昔から国家メディアとか宣伝装置が絶対的権威だった事実なんて脇へ追いやられて語られる気配もしちゃう。しかしまあ……すでに誤情報なんて当時から蔓延していたし。それこそ、ときには戦争原因にすら発展した例も見逃せない。ほら、『The Sound of Silence』をSimon and Garfunkel で聴くじゃない? あの歌詞ひとつ噛み締めながら現代を思い返している自分——なんとなくだけど、深い接点を感じざるを得なくなることもある。ま、いいか。
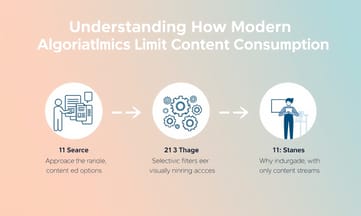
政治や世代間で語られる情報統制・偏見問題を考えてみよう
私たちの世代に向けられる非難なんて、いや、正直言ってね、こういう出来事は以前にも何度か目にしてきたと思うんだよな。まあ、大抵の場合は知らないふりしちゃう人もいるわけだけど——次の要点に移るしかない。## 本質的な問題点は、不透明さが漂い続けているところじゃないかと感じる。アルゴリズムという言葉自体、その定義や概要だけは分かったようで分からぬまま世間には溢れている。でも実際、調べれば調べるほど、「アルゴリズム」や「機械学習」の表面的な解説ばかり出てくるわけで、その仕組みが現実にどう動いているのかとなると…手応えがほとんど掴めないままだった、自分でも呆れちゃうくらい。それなのに不意に——誰もが知っていることとして、一見便利そうなシステムがユーザー一人ひとりの行動ややり取りを綿密に記録しながら、少しでも長くアプリ内で時間を過ごすようコンテンツ推薦を続けていたりする。こんなの有名だけど、それですら、本当に必要十分とは到底思えなくてさ。
一般公開されていないアルゴリズムについて、「政治的対立をさらに激しく煽っている」という指摘も後を絶たず、また利用者自身が明確に「もう興味ありません」と選択したのにも関わらず——特定集団にはなお執拗に特定コンテンツを押し付けたりするケースも聞く。正直ここまで来ると、中毒性云々より「怒り」に火種を投げ込むタイプの内容だったりエコーチェンバー現象とかヘイトスピーチだったり、更には陰謀論・シャドウバニングによる偏った倫理観までも増幅していく側面まで……見逃せと言われても首肯できなくなるよね。不自然なくらい全部、「ポリティカル・コレクトネス」の旗印、それっぽいコミュニティガイドライン名義で日々堂々と繰り返されてしまってる。不条理だよ、ほんと。
一般公開されていないアルゴリズムについて、「政治的対立をさらに激しく煽っている」という指摘も後を絶たず、また利用者自身が明確に「もう興味ありません」と選択したのにも関わらず——特定集団にはなお執拗に特定コンテンツを押し付けたりするケースも聞く。正直ここまで来ると、中毒性云々より「怒り」に火種を投げ込むタイプの内容だったりエコーチェンバー現象とかヘイトスピーチだったり、更には陰謀論・シャドウバニングによる偏った倫理観までも増幅していく側面まで……見逃せと言われても首肯できなくなるよね。不自然なくらい全部、「ポリティカル・コレクトネス」の旗印、それっぽいコミュニティガイドライン名義で日々堂々と繰り返されてしまってる。不条理だよ、ほんと。
透明性の欠如がSNSプラットフォームに及ぼす影響を探ろう
いや、まったく皮肉な話だけどさ、どうにもあなたの出すコンテンツが大きな害を与えている、そのこと自体には無頓着なのに、平然と倫理を説こうとしている…そんな態度、やっぱり気になっちゃうんだよね。たとえばさ、そのアルゴリズムたちが実際どう動いてるのか聞くって、ごく当たり前のリアクションじゃない? 私はそう思うよ。そして、その内訳や仕組みをわざと明かさないでいるとなれば、それこそ倫理的にグレーな行いじゃないかと……うーん、まあそう感じてしまうわけ。仮に具体的な被害の事例なんかが出ているなら、それこそ重大な問題として扱われるはずだろうし。不思議だけど、この話題って別に一個のアプリ限定でもなんでもなくてね。結局似たような問題があちこちで渦巻いている印象ばっかり強まるんだ。でももう最近では、プラットフォーム全体で〈アイデンティティ〉そのもの――つまりユーザーも運営も含めて――かなり激変していると思わない? 十年前だったらさ、それぞれのSNSとかアプリにはまだ妙な独自色とか気配りが残っていた記憶があるんだけど。ま、いいか。

なぜ人気SNSは個性やコミュニティ色を失いつつあるのか問う
今のプラットフォームって、なんだかどれも同じような雰囲気が漂っている気がするんですよね。うーん、不思議と言えば不思議というか、とくにTumblrやPinterest、それからReddit、昔のYouTubeとかも――いや、正直これらって元々はすごくマニアックなコミュニティ向けで生まれたものだったのにさ。だけど、あれよあれよと利用者が増えてきてから、全体的に丸くなっちゃった印象が強いです。ちょっと前までは奇天烈な発言も混在していたけど、最近はやけに味気なくてミニマリズム重視って感じ?「ま、いいか。」と自分を誤魔化しそうになるけど、本音を言うなら以前みたいな“適当にふらりと自己表現”できる場所じゃなくなったんだろうな。もう一歩踏み込んで何かを届けたかったら本気で努力しないと目立たない、そんな土壌になってしまった感じです。それ自体を悪いことだとは断定できないし――ただもう、敷居は明らかに上がっています。正直、小ぢんまりしたネット上のコミュニティこそ、それぞれ固有のルールとか濃厚なユーザーとの距離感とか、ごく狭い好みへの偏愛によって実際はもっとヘルシーだったんじゃないかな……そう心底思います。
小規模コミュニティと健康的ネット文化の価値に気付こう
インターネットって、そもそもこんな感じで人がつながるために作られたんだよね…なんて言い出す人、きっとまだいると思う。まあ、今自分たちの目の前に広がってる商業主義バリバリで拡大された姿とは全然別物だけどさ。ふとした時に、「LinkedInって結局もうFacebookと何か違うの?」なんてぼんやり疑問が浮かぶ。自己アピールし放題な場を提供してるってこと以外に何か本質的な差異なんてあるんだろうか、とか。今じゃ“エンゲージメント至上主義”みたいなのが普通になっちゃっていて、そういう基準のコンテンツばっか優先されて見せられる構造になってしまったような…正直、そのあり様は別の言葉で言えば妙に“専門外”というか浅い感触にも聞こえる。でも、まあ個人的な見方だから、ま、それも一意見に過ぎない気もするけど。
## 失われたもの
色々なアプリケーション、案外「大人向け」だとか理由付けして大量のコンテンツを検閲したりする。でも現実問題として、その運用はめちゃくちゃ徹底されてないこと誰でも知ってるはず。仮に本気で厳格化を推し進めちゃったら、この手のプラットフォームにはもう回避できないようなしょっぱい損失が生じてしまうからなのかなぁ、とぼんやり思うところもある。(多分)
## 失われたもの
色々なアプリケーション、案外「大人向け」だとか理由付けして大量のコンテンツを検閲したりする。でも現実問題として、その運用はめちゃくちゃ徹底されてないこと誰でも知ってるはず。仮に本気で厳格化を推し進めちゃったら、この手のプラットフォームにはもう回避できないようなしょっぱい損失が生じてしまうからなのかなぁ、とぼんやり思うところもある。(多分)
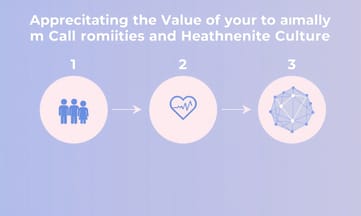
大手SNS同士が似通う理由とユーザーエクスペリエンス変化を見る
「子ども向けじゃない」ってうたってるガイドライン、正直言って内容も解釈も曖昧だし、一貫してないよなぁと思わされることが多い。いや、それでいて実際には同じプラットフォーム内に、全く管理されてない大人向けのものと平然と子ども用コンテンツが共存してる現実を目にすると、さすがに引っかかるんだけど…なんだろう、この違和感。しかもさ、そのアルゴリズム自体、中立とか透明性とか微塵も感じられなくて、とても納得できそうになくてさ。ま、どうにもならない気配すらある。
最近は、本当にあからさまに子どもをターゲットにしているメディアパーソナリティやクリエイターばっかり増えてきたなと感じる。その一方で(なんかこう…嘆かわしいよね)、今の子どもたちは昔より豊かなネット体験を手にする機会そのものが失われつつある気がしてならない。それこそ、自分たちの世代が小さい頃普通に触れられたインタラクティブ系ウェブサイト―例えばクラブペンギンみたいなの、知ってる? ああいうやつって妙に懐かしくなる瞬間があるんだけど…。
考えてみれば、当時はお気に入り番組や映画、それから絵本キャラなど色々なテーマを持ったウェブサイトが無数に存在した。そういったところでは、パズル的なゲームやカスタマイズ要素、それから仮想ペット育成とか家作り遊びみたいなのまで幅広く盛り込まれていて…。単なるフラッシュゲーム集として雑然と設計された意味不明なランダムサイトですら、不思議と心には刺激になったというか——そんな些細な刺激さえ今となっては眩しく映ってしまう、自分でもどうしてこんな話になるのか分からないけど、とりあえず書き留めておきたい気分だった。ま、いいか。
最近は、本当にあからさまに子どもをターゲットにしているメディアパーソナリティやクリエイターばっかり増えてきたなと感じる。その一方で(なんかこう…嘆かわしいよね)、今の子どもたちは昔より豊かなネット体験を手にする機会そのものが失われつつある気がしてならない。それこそ、自分たちの世代が小さい頃普通に触れられたインタラクティブ系ウェブサイト―例えばクラブペンギンみたいなの、知ってる? ああいうやつって妙に懐かしくなる瞬間があるんだけど…。
考えてみれば、当時はお気に入り番組や映画、それから絵本キャラなど色々なテーマを持ったウェブサイトが無数に存在した。そういったところでは、パズル的なゲームやカスタマイズ要素、それから仮想ペット育成とか家作り遊びみたいなのまで幅広く盛り込まれていて…。単なるフラッシュゲーム集として雑然と設計された意味不明なランダムサイトですら、不思議と心には刺激になったというか——そんな些細な刺激さえ今となっては眩しく映ってしまう、自分でもどうしてこんな話になるのか分からないけど、とりあえず書き留めておきたい気分だった。ま、いいか。
未成年者保護と曖昧なコンテンツ規制基準の実情を調べてみる
これは、単純にコンテンツを「消費」することとは全然違ったんだよね。たぶんだけど、僕らは遊んでいたし、学びもしていたし、それから──まあ時には考えたりもして、本当に探そうとしてた気がする。でも当時さ、子供っていう立場から無理やり大人の世界へ踏み出す必要なんてまるで感じなかったと思う。どうしてかというと、その頃って、大人と子供の間にピシッと境界線引かれたようなオンラインコミュニティがちゃんとあって、それぞれ住み分けてた雰囲気だったもの。
それがさ、今になると何となく……うーん、「巨大でぐちゃぐちゃしたファミリーギャザリング」の渦中に投げ込まれている感覚になる。不思議なもんだよ。誰にも気まずい思いをさせず話すのが難しくなるし、大人はしょうもない政治ネタばっか続けるの控えたい(本人だって分かってるはず)、逆に本来遊ぶ側であるはずの子供らが余計な大人のお喋り耳にしてばっかなんだろうね。「ま、いいか。」とか内心呟きつつ、自分自身どこまで何を楽しめているのかわからなくなる。
## あなたのデータはあなたの手元になく
…いや、その、「同意」はちゃんとしてるつもりでも、自分のデータ管理され方とか売り飛ばされる可能性についてほんとのところ把握してないよね。それに実際、この手のデータは完全に消去された!なんて到底言えなくて。何年経とうが自分の好みとか政治観とか宗教的スタンス、クセみたいなのや反応パターン――要するに、人柄丸ごと全部ずっと記録され続けていくわけで、その使われ方や保存理由すら結局曖昧模糊で、誰にも説明尽くせない状況というか…ため息しか出ない日も多い。
それがさ、今になると何となく……うーん、「巨大でぐちゃぐちゃしたファミリーギャザリング」の渦中に投げ込まれている感覚になる。不思議なもんだよ。誰にも気まずい思いをさせず話すのが難しくなるし、大人はしょうもない政治ネタばっか続けるの控えたい(本人だって分かってるはず)、逆に本来遊ぶ側であるはずの子供らが余計な大人のお喋り耳にしてばっかなんだろうね。「ま、いいか。」とか内心呟きつつ、自分自身どこまで何を楽しめているのかわからなくなる。
## あなたのデータはあなたの手元になく
…いや、その、「同意」はちゃんとしてるつもりでも、自分のデータ管理され方とか売り飛ばされる可能性についてほんとのところ把握してないよね。それに実際、この手のデータは完全に消去された!なんて到底言えなくて。何年経とうが自分の好みとか政治観とか宗教的スタンス、クセみたいなのや反応パターン――要するに、人柄丸ごと全部ずっと記録され続けていくわけで、その使われ方や保存理由すら結局曖昧模糊で、誰にも説明尽くせない状況というか…ため息しか出ない日も多い。

子ども向けデジタル体験がどう変わったか比べて発見しよう
正直なところ、最近気づいたのだが──いや、もしかしたら前から何となく感じていたけど──いま使ってるアプリって、自分自身の家族よりも私について把握しているんじゃないかと思う時がある。ま、それも妙な話だけど。GDPR(General Data Protection Regulation)のような欧州連合におけるプライバシー保護法に関する話題はよく耳にするものの、その現実を真正面から受け入れることはずっと抵抗感が強かったし、まあ実際今でも整理できてない。
でもね、不思議とこれらの規制はソーシャルメディアで動いている根っこのアルゴリズム自体にメスを入れてはいない……うーん、本当にそう言えるんじゃないかな?表向きには同意取得やデータへのアクセス許可みたいなことばかりが重視されていて、その集めたデータがどういう使われ方をし、表示内容とか人それぞれの信念形成まで及ぶ影響はほとんど顧みられていないように感じる。
たとえば企業側が「ちゃんと法律守ってます」って胸張ったとしても、結局その裏では技術的にも合法的にも人々の情報収集や観察は続行可能で、人間の行動や信じ込みすら操る力学は消えていない。むしろ目的自体、「ユーザーの日々の行動予測」と「エンゲージメント維持」に尽きるんじゃ?ああ、このやりきれなさというか、曖昧模糊としたアルゴリズムのおかげで生まれる副作用こそ、本来もっと騒がれるべきジレンマなんだと思う。あれ、語りすぎちゃったかな…。
でもね、不思議とこれらの規制はソーシャルメディアで動いている根っこのアルゴリズム自体にメスを入れてはいない……うーん、本当にそう言えるんじゃないかな?表向きには同意取得やデータへのアクセス許可みたいなことばかりが重視されていて、その集めたデータがどういう使われ方をし、表示内容とか人それぞれの信念形成まで及ぶ影響はほとんど顧みられていないように感じる。
たとえば企業側が「ちゃんと法律守ってます」って胸張ったとしても、結局その裏では技術的にも合法的にも人々の情報収集や観察は続行可能で、人間の行動や信じ込みすら操る力学は消えていない。むしろ目的自体、「ユーザーの日々の行動予測」と「エンゲージメント維持」に尽きるんじゃ?ああ、このやりきれなさというか、曖昧模糊としたアルゴリズムのおかげで生まれる副作用こそ、本来もっと騒がれるべきジレンマなんだと思う。あれ、語りすぎちゃったかな…。
個人データ利用と法律上コントロール不足への課題意識を持とう
現状の法律にそのまま従うべきなのか、それともやっぱり、この問題への対策として新しい法規や制約を探るべきなのか…なんていう問いが今投げられている。正直、議論で指摘されている諸問題について共通理解が無ければ、結局グレーな運用はこれからも何となく続いていっちゃう気がするんだよね。まあ、仕方ないのか? それに加えてプラットフォーム側が「変更点について説明しません」って態度を取ってしまうとさ、いつの日か利用者向けの情報提供さえも断絶されるなんてありそうだなと思ったりして。
テクノロジー業界全体がこの種のあいまいさを普通に容認している事実にもどうにも腑に落ちないものが残る。例えば法律の場合には成立した全文がオープンになるじゃないか。でも、アルゴリズムの話題になった瞬間、「そもそもアルゴリズムとは?」的な抽象的で掴み所のない解説しか出回らなくなって、本当に個々のプラットフォーム内でどんな仕組みになっているのか――そこだけはずっと覆い隠されたままだ。想像してほしいんだけど、もし仮に立法者たちが市民へ政策説明を行う際に、「法律そのものとは何です」とだけ言って中身自体は一切見せようとしないなら、その閉鎖性は到底許容できるものじゃないと思う。それと似たような不透明さが知らず知らず認められつつある、それが現実なのかな…。ま、いいか。
テクノロジー業界全体がこの種のあいまいさを普通に容認している事実にもどうにも腑に落ちないものが残る。例えば法律の場合には成立した全文がオープンになるじゃないか。でも、アルゴリズムの話題になった瞬間、「そもそもアルゴリズムとは?」的な抽象的で掴み所のない解説しか出回らなくなって、本当に個々のプラットフォーム内でどんな仕組みになっているのか――そこだけはずっと覆い隠されたままだ。想像してほしいんだけど、もし仮に立法者たちが市民へ政策説明を行う際に、「法律そのものとは何です」とだけ言って中身自体は一切見せようとしないなら、その閉鎖性は到底許容できるものじゃないと思う。それと似たような不透明さが知らず知らず認められつつある、それが現実なのかな…。ま、いいか。


















































