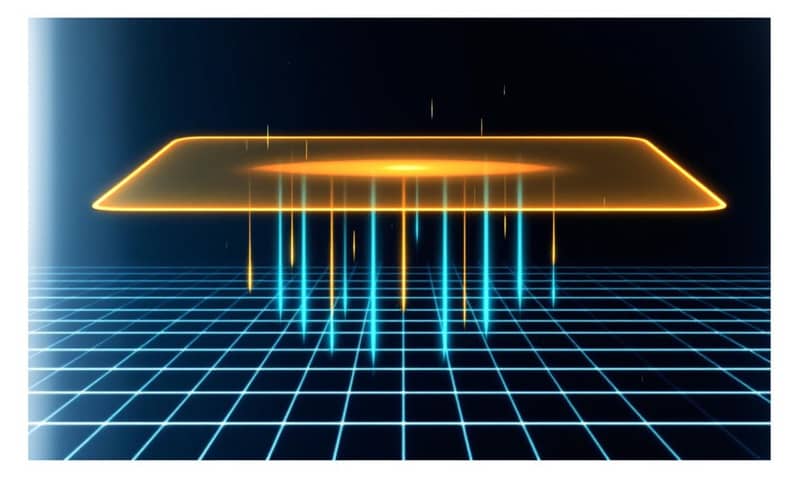うーん、最近よく考えてるんだけど、レイヤー2の話。みんな、速いとか、ガス代が安いとか、そういう話ばっかりするじゃないですか。まあ、もちろんそれも大事なんだけど…なんか、もっと本質的なことを見逃してる気がして。特に、Arbitrumを見てるとそう思うんだよね。
これって、単にイーサリアムをスケールさせるための「拡張パーツ」って話じゃない気がするんだ。もっと大きな、なんていうか…開発者のための新しい「土壌」を作ろうとしてる感じ。うん、多分そんな感じ。
重点一句話
正直、Arbitrumの未来は「速さ」じゃなくて、「今までブロックチェーンを触らなかった開発者を、どうやって呼び込むか」にかかってると思う。
もうすでに起きてること、知ってる?
まあ、数字の話からすると、確かにすごい。TVL(預かり資産)が200億ドルを超えてて、レイヤー2の中じゃダントツ。OptimismとかBaseとか、他の競合をぶっちぎってる。これは事実。でもね、僕が面白いと思うのはそこじゃないんだ。
例えば、海外の巨大掲示板のRedditが、コミュニティのポイントシステムをArbitrum Nova上で動かしてるって話。これ、すごくない? DeFiみたいな金融取引だけじゃなくて、もっと身近な、ソーシャルな用途で使われ始めてるっていう証拠だから。ガス代がめちゃくちゃ安いNovaだからできることだよね。
あとね、最近だと「Converge」っていう新しいブロックチェーンの話。これはもっとすごい。現実世界の資産…そう、Real-World Asset、RWAってやつをトークン化するための専用チェーンみたいなもので。Securitizeとかと組んで、70億ドル規模の安定資産をDeFiに持ち込もうとしてる。これって、もう暗号資産の世界だけで完結する話じゃなくなってきてるってことなんだよね。
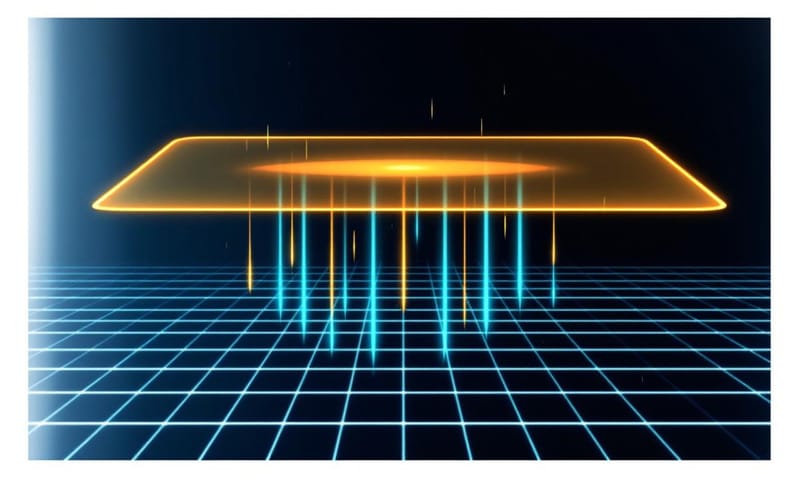
で、どうやってそれを実現してるの?
こういう未来を実現するための、まあ、設計図みたいなものがいくつかあって。ここが一番大事なところだと思う。
カスタムチェーンを作れる「Arbitrum Orbit」
まず、Arbitrum Orbit。これは、なんて言えばいいかな…「自分だけの専用高速道路を作れるキット」みたいなもの。普通、レイヤー2って言ったら、みんなで一本の大きな道路を共有するイメージじゃないですか。でもOrbitを使うと、プロジェクトごとに最適化された独自のレイヤー2、あるいはレイヤー3チェーンを立ち上げられるようになる。
例えば、ゲーム会社なら、大量のトランザクションを低遅延でさばくことに特化したチェーンを作れる。金融機関なら、プライバシー機能を強化したチェーン、とかね。これ、めちゃくちゃ大きい変化だと思う。Offchain Labsが作ったコードをフォークして、自分たちのニーズに合わせてカスタマイズできる。イーサリアムのセキュリティを借りながら、自由な設計ができるっていうのがミソ。
しかも、最近じゃ「Orbitのチェーンをイーサリアム以外のブロックチェーン、例えばCosmosとかにも広げていこう」みたいな提案も出てきてる。そうなるともう、Arbitrumはイーサリアムの拡張機能っていうより、いろんなチェーンをつなぐ「ハブ」みたいな存在になるかもしれない。
個人的に一番ヤバいと思ってる「Stylus」
で、次がStylus。正直、これが僕にとっては一番のゲームチェンジャーかもしれない。何かというと、スマートコントラクトをいろんな言語で書けるようになるっていうアップデート。
今まで、ブロックチェーンで何か作ろうと思ったら、ほぼSolidityっていう言語を覚えるしかなかった。これって、開発者にとっては結構な参入障壁だったと思うんだ。でも、StylusはRustとか、C、C++みたいな、もっと一般的な言語に対応する。これ、わかるかな…?今までブロックチェーンに興味なかった、例えばゲーム業界のベテランプログラマーとか、AIの研究者とかが、「あ、俺の知ってる言語で書けるなら、ちょっとやってみようかな」ってなる可能性があるってこと。
技術的には、WebAssembly (WASM) を使って、EVMよりも効率的にコントラクトを実行するらしい。だから、ガス代も安くなるし、処理も速くなる。特にAIみたいに計算量がめちゃくちゃ多いアプリケーションには、すごい朗報だと思う。

結局、どのArbitrumを使えばいいの?
ここまで聞いて、「OneとかNovaとかOrbitとか、色々あってわからん!」ってなってる人もいると思う。まあ、そうだよね。すごくざっくり、僕なりの解釈で比較してみると、こんな感じかな。
| 種類 | 一言でいうと… | 向いてる用途 | 僕の勝手なコメント |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | ザ・メインストリート。みんなが使う汎用道路。 | DeFiプロトコル全般。UniswapとかAaveとか。 | まあ、とりあえず迷ったらこれ。一番実績あるし、安定してる。でも、ガス代は他よりちょっとだけ高いかも。 |
| Arbitrum Nova | ゲームとSNS用の超格安レーン。 | ブロックチェーンゲーム、ソーシャルアプリ、NFTの大量配布とか。 | 「AnyTrust」っていう技術で、データを全部オンチェーンに書かないから安い。その分、分散性は少し犠牲になってるけど…ゲームのスコア記録とかに、そこまでガチガチの分散性いる?って話。うまい割り切りだと思う。 |
| Arbitrum Orbit | オーダーメイドのプライベートサーキット。 | 特定のニーズを持つ企業、大規模ゲーム、金融機関のコンソーシアムチェーン。 | これはもう、我々一般ユーザーが直接使うってより、デカいプロジェクトが「自分たちの国を作る」みたいなイメージ。将来、面白いものはここから出てくるかもね。 |
もちろん、良いことばかりじゃない
ここまで持ち上げてきたけど、もちろん課題もある。というか、結構クリティカルなやつも。
一番よく言われるのが、出金に7日間かかる問題。これ、Optimistic Rollupsの仕組み上、仕方ないんだけどね。「不正がなかったか」を検証するための期間が必要で。でも、すぐにお金動かしたいユーザーからしたら、やっぱり不便。zk-Rollups系のレイヤー2(zkSyncとかStarkNetとか)は即時出金できるから、ここは明確な弱点。
あと、まあ、これはArbitrumだけの話じゃないけど、レイヤー2が増えすぎて、資産がいろんなチェーンに分散しちゃう「流動性の分断」っていう問題もある。あっちのチェーンではこのトークンが使えるけど、こっちでは使えない…みたいな。ただ、ArbitrumはTVLでトップを走ってるから、今のところは「とりあえずArbitrumに資産を置いておけば間違いない」っていう状況にはなってるけどね。
競争も激しいし。さっき言ったzk-Rollupsは、長期的にはこっちが本命だって言う人も多い。技術的にもエレガントだし。だから、Arbitrumが今の地位を保ち続けられるかは、正直、誰にもわからない。結構な競争の真っただ中にいるってことは、忘れちゃいけない。

じゃあ、これからどうなる?
うーん、結局のところ、Arbitrumが目指してるのは、イーサリアムの「スケーリング問題」を解決するだけじゃないんだと思う。もっと先の、Web3のエコシステム全体を見据えてる。
Stylusで開発者の裾野を広げて、Orbitで特定用途のチェーンをどんどん作ってもらう。そうやって、金融だけじゃなく、ゲーム、ソーシャル、AI、現実資産のトークン化…あらゆる分野で「ブロックチェーンを使うのが当たり前」な世界を作ろうとしてるんじゃないかな。
特に、日本の状況と照らし合わせると面白いかも。日本ではまだ、暗号資産っていうと投資とか投機のイメージが強いじゃないですか。でも、海外だと、Redditの例みたいに、もっと生活に根付いたユーティリティとしての使い方が模索されてる。そのプラットフォームとして、Arbitrumが選ばれてるっていうのは、結構大きな意味があると思う。これは、日本の大手暗号資産メディア、例えばCoinPostとかでも最近よく取り上げられてるテーマだよね。
だから、僕たちがArbitrumを見る時も、単に「$ARBトークンの価格がどうなるか」とか、「他のレイヤー2より速いか遅いか」だけじゃなくて、「このプラットフォームの上で、これからどんな新しいアプリケーションが生まれるんだろう?」っていう視点で見るのが、一番面白いんじゃないかな。うん、僕はそう思ってる。
ちょっと考えてみてほしいんだけど…
もしあなたが開発者だったら、StylusでRustやC++が使えるようになったら、「ブロックチェーン上で何か作ってみたい」って思いますか? それとも、やっぱり7日間の出金問題とか、他のハードルの方が気になりますか?
開発者じゃない人も、もし身近なサービス(例えば好きなゲームとかSNSとか)がArbitrum上で動くようになったら、使ってみたいと思いますか? ぜひ、あなたの意見を聞かせてください。