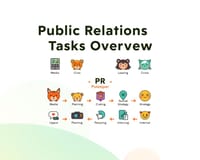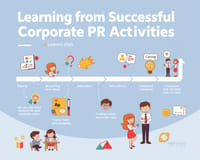ここから始めよう - 広報活動の効果をすぐ実感できる実践ガイド
- 広報の目的を3項目以内に書き出す
方向性がぶれず、施策ごとの成果比較もしやすくなる
- ターゲット層の年齢・興味関心で2カテゴリに分け直す
訴求力が上がり、情報発信後7日以内の反応率向上へつながる
- 発信する情報を毎月1回は見直し不要な内容は削除
常に鮮度ある話題だけ届けられ、社内外からの信頼も安定する
- `SNSまたはメール配信`など主要チャネルで週1回以上発信予定を入れる
"定期的な接点"維持で半年後まで記憶・認知されやすい状態になる
現場の違和感、数字じゃ測れない価値
「社内外のコミュニケーションが企業価値に直結する」とか、最近よく耳にするけど、ほんとうにそうなんだろうか、とか思いつつ…まあ、現実はもうそんな空気になってるんだよね。情報発信部門というと、昔ならただの広報担当って感じだったけど、今じゃ経営戦略やらブランド構築とかにも影響与える立場になったらしい。ああ、何書いてたっけ……うーん、それでもやっぱりビジネス環境って流動的で、市場とか社会の変化が組織内部にも連鎖して染み出してきているような。
部署ごとの温度差とか現場感覚のズレ――見えづらくなってきてる印象あるんだよね。これもまた曖昧だけど…。例えばさ、国内の総合調査会社が2023年に調べたデータによれば、「企業広報担当者の約三成が部門間調整に課題を感じている」って話もあるし。それ聞いた瞬間に納得しかけたけど、一瞬だけ猫動画見てしまった…。で、その後KPIだけじゃ測れない非数値的要素への配慮?それが今まで以上に求められてるわけで。ま、いいか。また話戻すと、結局そこをどう扱うか悩ましい時代なんだなって思ったりする。
部署ごとの温度差とか現場感覚のズレ――見えづらくなってきてる印象あるんだよね。これもまた曖昧だけど…。例えばさ、国内の総合調査会社が2023年に調べたデータによれば、「企業広報担当者の約三成が部門間調整に課題を感じている」って話もあるし。それ聞いた瞬間に納得しかけたけど、一瞬だけ猫動画見てしまった…。で、その後KPIだけじゃ測れない非数値的要素への配慮?それが今まで以上に求められてるわけで。ま、いいか。また話戻すと、結局そこをどう扱うか悩ましい時代なんだなって思ったりする。
テンプレ頼り?戦略の個別調整が鍵に
「広報戦略の違いって、現場経験に如実に出るものだよ」と、なんだかんだ専門家はみんな言いたがるんだよね。うーん、たしかにそうかも…と思いつつも、自分は今ひとつピンと来ない時もある。でもまあ、ベテランの担当者となると、やっぱり情報をどう届けるか、その相手の状況とか伝えるタイミングによって誤解が起きやすいことを結構気にするんだ。いや、それだけじゃなくて、一斉配信したところで「自分ごと」にはなりづらい壁があったりしてさ…。
例えばさ、伝達したあとで個別フォローをしたりとか、部署ごとに優先順位を付け直してみたりとか、本当に細かく設計し直して対応策作ってる姿を目撃すると、「ここまでやらなきゃダメなの?」なんて思っちゃう時も正直ある。ああ、ごめん話それた。でも結局また本題戻すけど、新任担当者になると逆に定型文だったり既存テンプレートへの依存度がぐっと高まっちゃうみたいなんだ。本来必要な柔軟性とか現場適応力みたいなものが発揮されないこともしばしばある、と聞いたことがある。
この辺の違いというものをちゃんと理解して、自社独特の組織課題だったり文化だったり―うーん、そのへん難しいけど―そこに合わせて戦略調整することこそ、この先ますます大事になっていく気がする。ま、いいか。
例えばさ、伝達したあとで個別フォローをしたりとか、部署ごとに優先順位を付け直してみたりとか、本当に細かく設計し直して対応策作ってる姿を目撃すると、「ここまでやらなきゃダメなの?」なんて思っちゃう時も正直ある。ああ、ごめん話それた。でも結局また本題戻すけど、新任担当者になると逆に定型文だったり既存テンプレートへの依存度がぐっと高まっちゃうみたいなんだ。本来必要な柔軟性とか現場適応力みたいなものが発揮されないこともしばしばある、と聞いたことがある。
この辺の違いというものをちゃんと理解して、自社独特の組織課題だったり文化だったり―うーん、そのへん難しいけど―そこに合わせて戦略調整することこそ、この先ますます大事になっていく気がする。ま、いいか。
Comparison Table:
| 評価軸 | 具体的な指標 | 重要性 | 考慮すべき要素 | 推奨される施策 |
|---|---|---|---|---|
| エンゲージメント率 | 1カ月間投稿20本・約五分の一超 | 数値そのものではなく内訳が重要 | ポジティブとネガティブの混在を分析する必要がある | コメント内容を細かく分析する |
| 情報配信方法 | 一律配布型 vs. パーソナライズ戦略 | 全員に同じ情報提供は必ずしも正しいとは限らない | 受け手の理解度や関心度を考慮する必要がある | 双方向チャネルの設計 |
| コミュニケーション質向上法 | 受信者ごとの心理状態に寄り添うこと | |||
| フォローアップ設計 | アンケート回収やQ&A窓口の事前準備 | |||
| 反応率向上策 | 短尺動画と即時フィードバック機能の活用 |

サイロ化とKPI依存、その見えぬ落とし穴
最近、現場のマネージャーから「部署ごとのサイロ化が広報活動の一番の障壁だよ」と直接耳にすることが増えてきた。うーん、確かにそうかも。各部門がバラバラに情報発信を進めてしまうと、全社メッセージってどうしても統一感を保ちづらくなるし…あ、いや、それだけじゃなくて、有事になると意思決定スピードまで遅れ気味になる傾向もあるみたいなんだ。まったく面倒なものだ。
それから、「KPIドリブン」に偏りすぎるケースでは、本来大切にすべき信頼醸成や潜在的不満への細かな対応がおざなりになっちゃってさ、表面的には数値達成で問題ないように見えるけど実際は現場レベルで違和感とか摩擦とかが残ること、多いらしい。えっと…ああ脱線した。でもまあ、その話は結局つながっているわけで。
組織運営研究(国内大手企業領域・直近数年)でもね、この状況下では中長期的なガバナンス力低下やリスク管理機能の弱体化について指摘されていたりする。本当に疲れる話だけど…。やっぱり持続的な広報基盤を築いていこうと思えば、根本課題への具体的対応策設計こそ不可欠になってくるんだろう、とぼんやり考えてしまった。ま、いいか。また明日も似たような話を聞くだろうし。
それから、「KPIドリブン」に偏りすぎるケースでは、本来大切にすべき信頼醸成や潜在的不満への細かな対応がおざなりになっちゃってさ、表面的には数値達成で問題ないように見えるけど実際は現場レベルで違和感とか摩擦とかが残ること、多いらしい。えっと…ああ脱線した。でもまあ、その話は結局つながっているわけで。
組織運営研究(国内大手企業領域・直近数年)でもね、この状況下では中長期的なガバナンス力低下やリスク管理機能の弱体化について指摘されていたりする。本当に疲れる話だけど…。やっぱり持続的な広報基盤を築いていこうと思えば、根本課題への具体的対応策設計こそ不可欠になってくるんだろう、とぼんやり考えてしまった。ま、いいか。また明日も似たような話を聞くだろうし。
初動で差がつく設計、A/Bテストの実例から
「そもそも“どこから始める?”って、ああ、また誰かに聞かれた気がする。でも実際、自分でやってみると順序の設計が想像以上に大事だったんだよね。まず伝達対象を丁寧に洗い出して、そのあとで“誰に”とか、“どんな順番で”とか、“どのメッセージ設計で”伝えるかをざっくり並べて可視化してみる。ま、完璧じゃなくても、とりあえず並べるだけでもかなり頭の中が整理されて、情報の迷子になる確率は明らかに減った感じがするんだよな。まあ…それでも思考が散らばる時あるけど。そういえば前にさ、ほぼ半分くらいの部署メンバー相手に初動案A/Bテスト方式で資料配布したことがある。うーん、その直後に匿名フィードバック集めてみたら、「この言い回しだと別部署には全然響かなかった」とか「最初の順番変えたほうが分かりやすくなると思います」とか、不意打ちみたいなコメントがポロッと出てきたりしたんだよね。それ見て、一瞬だけ心折れそうになったけど…。分析までやろうとすると数週間単位は普通に必要なんだけど、小規模チームなら工数的にもそんな重くないし(いや、人によるかも)。要は細部まで詰め切らず、とりあえず仮説投げて改善点を拾っていく。その繰り返ししかない、というか、それしか思いつかなかったし…。ま、いいか。
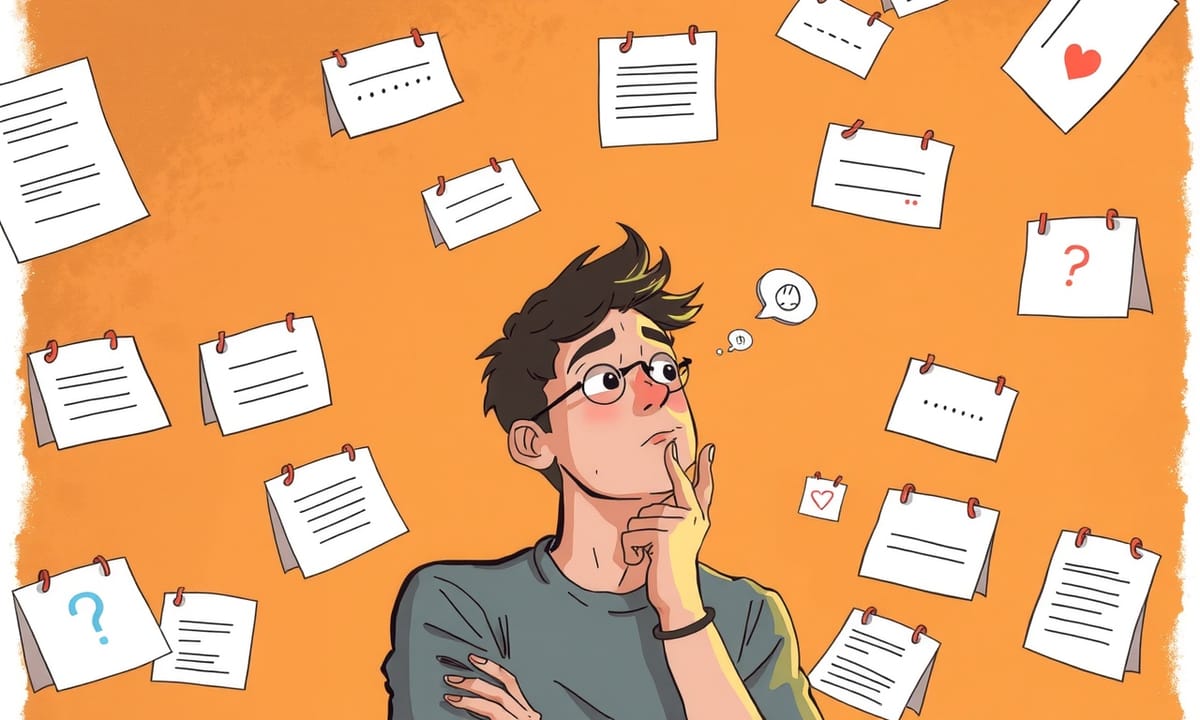
中小企業流・少人数でも効くチャネル選定術
「限られたリソースでも最大効果を目指す」っていう発想で現場の広報業務を考え始めると、うーん…やっぱり中小企業の場合は“チャネル数を無闇に増やすよりも選択肢を絞る”ほうが最終的に成果につながりやすい、そんな気がする。いや、なんでかって?大手みたいにSNSを何個も一斉に更新しようと思ったら、正直人的にも時間的にもきつくなるし、それなら既存顧客向けメルマガとか取引先だけが入れるLINEグループとか、身近なコミュニティ型チャネルへ思い切って重心移した方が結局ラクだったりして。あ、そういえばこの話題とは直接関係ないけど最近スマホの充電忘れ多くて困ってる…。ま、それはさておき——実際、「七十多」と呼ばれるくらいの中小規模事業者ではダイレクトPRや口コミ活用が工数対効果の面で有利だよねという声も多い(中小支援団体・直近調査)。全方位展開、と言葉では簡単だけど、結局自社顧客像から逆算して“どこに集中投下するか”明確化することこそが現場運用のカギになるっぽい。ま、いいか。
エンゲージメント率だけじゃ見えない落とし穴
「SNS運用効果の検証について、『1カ月間投稿20本・エンゲージメント率が約五分の一超』みたいな具体的な指標がよく挙げられるけど、まあ、確かに目安としては分かりやすい。でも、ほんとに大事なのはリアクション数値そのものじゃなくて、その内訳をどこまで細かく見て突き詰められるか…なんだよね。ああ、ちょっと話逸れるけど、最近は数字だけ追いかけても全然納得できないことばっかりだし。で、例えばさ、コメント欄が賑わってるって言っても、中身ちゃんと見るまではポジティブとネガティブが混ざってたりすること多いんだ。
うーん、それ考えると、一つひとつの投稿ごとにコメント内容とか言及傾向までバラして分析しないと、『拡散された=好意的評価』とは決してならない現実を忘れちゃいけないと思うんだよね。ま、いいか。えっと、それを前提に評価軸を作らなきゃ意味がない。で、このプロセス省略しちゃうと、その場限りのバズだけで終わっちゃって、本来重視すべき継続的なブランド支持とかリピート行動には結び付かなくなるという話。
現場では反応数値だけ眺めて満足するんじゃなく、“質”にも深く切り込んで検証していかなきゃならない――たぶん、それ抜きには見えてこないこと、多すぎるからさ。」
うーん、それ考えると、一つひとつの投稿ごとにコメント内容とか言及傾向までバラして分析しないと、『拡散された=好意的評価』とは決してならない現実を忘れちゃいけないと思うんだよね。ま、いいか。えっと、それを前提に評価軸を作らなきゃ意味がない。で、このプロセス省略しちゃうと、その場限りのバズだけで終わっちゃって、本来重視すべき継続的なブランド支持とかリピート行動には結び付かなくなるという話。
現場では反応数値だけ眺めて満足するんじゃなく、“質”にも深く切り込んで検証していかなきゃならない――たぶん、それ抜きには見えてこないこと、多すぎるからさ。」

一律配布は危険?個別心理へのカスタマイズ力
「全員に同じ情報を一斉に届ければ安心」って、たしかによく言われるけど…現場ではそれが必ずしも正しいとは限らないんだよね。いや、むしろ、それでトラブルが起きることもあるし。例えばさ、社内ポータルで通知だけを流す“一律配布型”。えっと……まあ、一見合理的に思えるけど、実際は受け手の理解度とか関心度まで気にしていないことが多いじゃん?なんかこう、「誰もがちゃんと読んで反応する」と信じたい気持ちはわかる。うーん、でも主体性ってそう簡単には出てこないよな。
それにさ、曖昧な表現や行間頼みのメッセージって──あれ、不安になる人もいるし責任転嫁の温床にもなる。ああもう、この辺り結構モヤモヤする。伝える側はつい「これくらい分かるだろう」って思っちゃう。でも違うよね…。内容の取り違えとか、不必要な緊張感まで生まれる可能性が高い。ふと思ったけど、自分でも前職時代そんな失敗した記憶あるな。
だからこそさ、それぞれの立場や状況について個別に理解しようと努めたり──いやまあ全員分やるのは面倒だけど、本当に大切だと思う。その上で双方向チャネルを設計すること、これが不可欠なんだろうな…たぶん。一瞬話逸れるけど、「適切な伝達方法や語調」を相手ごとにカスタマイズできる力、それこそ本質的な差別化につながる要素なんじゃないかなぁ、と最近特によく感じている。また脱線したけど、ともかく“受信者ごとの心理状態”への寄り添い方次第で、コミュニケーションそのものの質も随分変わるものだよね。ま、いいか。
それにさ、曖昧な表現や行間頼みのメッセージって──あれ、不安になる人もいるし責任転嫁の温床にもなる。ああもう、この辺り結構モヤモヤする。伝える側はつい「これくらい分かるだろう」って思っちゃう。でも違うよね…。内容の取り違えとか、不必要な緊張感まで生まれる可能性が高い。ふと思ったけど、自分でも前職時代そんな失敗した記憶あるな。
だからこそさ、それぞれの立場や状況について個別に理解しようと努めたり──いやまあ全員分やるのは面倒だけど、本当に大切だと思う。その上で双方向チャネルを設計すること、これが不可欠なんだろうな…たぶん。一瞬話逸れるけど、「適切な伝達方法や語調」を相手ごとにカスタマイズできる力、それこそ本質的な差別化につながる要素なんじゃないかなぁ、と最近特によく感じている。また脱線したけど、ともかく“受信者ごとの心理状態”への寄り添い方次第で、コミュニケーションそのものの質も随分変わるものだよね。ま、いいか。
動画PR投入で見えた成功例とブームの罠
「動画プロモーションを導入してから、だいたい一ヶ月くらいでリーチ数が七割近く伸びたんですよ」と担当者が話していた。ああ、でも隣の部署では特に何も変わらなかったらしい。なんだかなぁ、分野とか国によって本当に反応バラバラみたいで、正直ちょっと拍子抜けする。でもまあ、それぞれ現場の空気感って違うし…うーん、そこで少し考えちゃった。
実は昔は「とにかく全員に通知送れば大丈夫」みたいな古式ゆかしいやり方が主流だったんだけど、最近は個々の受信スタイル?それに合わせて工夫する流れが目立ってきた気がする。例えば一部のチームでは短尺動画と個別フィードバックを組み合わせて関心維持を狙ったりしてるみたい。でも逆に、その盛り上がりばっかり追い求めちゃって、“ブーム終わったら誰も反応しない”というパターンもまあまあよく見る。
ま、いいか。結局、「地味でもコミュニティ的な積み重ね、大事ですね」なんて振り返る声もちらほら出ているそうで…。ほんと、それだよな、とつい頷いてしまう自分がいる。
実は昔は「とにかく全員に通知送れば大丈夫」みたいな古式ゆかしいやり方が主流だったんだけど、最近は個々の受信スタイル?それに合わせて工夫する流れが目立ってきた気がする。例えば一部のチームでは短尺動画と個別フィードバックを組み合わせて関心維持を狙ったりしてるみたい。でも逆に、その盛り上がりばっかり追い求めちゃって、“ブーム終わったら誰も反応しない”というパターンもまあまあよく見る。
ま、いいか。結局、「地味でもコミュニティ的な積み重ね、大事ですね」なんて振り返る声もちらほら出ているそうで…。ほんと、それだよな、とつい頷いてしまう自分がいる。

パーソナライズ×双方向、次世代型コミュニケーションへ
「オーディエンスセグメントごとのパーソナライズ戦略」を採用した企業の実例について、西欧B2B市場調査(2025年)で少し見てみたんだけど、いや、正直こういうデータって半信半疑なとこもあるよね。でも、従来型の一斉配信方式よりもエンゲージメント率が約二割ほど高い傾向だと報告されている。ま、数字は数字か。
具体的には……えっと、ターゲット単位で内容や配信タイミングをきめ細かく調整しているらしい。それに短尺動画とか即時フィードバック機能――このあたりも現場で取り入れられてきてるんだよね。なんか最近ショート動画ばっかり目につくなって思ったけど、こういう流れなのかな。
逆に全員へ一律通知を続けた場合、「反応率が伸び悩む」と答えた担当者も一定数いたという話だ。しかしまあ、それって今さら感ある気がするけど……うーん、自分だけ?いや、ごめん、話戻すね。
今は単発的な施策から、中長期的な双方向コミュニケーションへの転換点とも言える、とそんな空気感が漂っているみたい。実はそうでもなくて…と言いたいところだけど、この調査ではそう示唆されてるし、とりあえず現状そんな感じかな。
具体的には……えっと、ターゲット単位で内容や配信タイミングをきめ細かく調整しているらしい。それに短尺動画とか即時フィードバック機能――このあたりも現場で取り入れられてきてるんだよね。なんか最近ショート動画ばっかり目につくなって思ったけど、こういう流れなのかな。
逆に全員へ一律通知を続けた場合、「反応率が伸び悩む」と答えた担当者も一定数いたという話だ。しかしまあ、それって今さら感ある気がするけど……うーん、自分だけ?いや、ごめん、話戻すね。
今は単発的な施策から、中長期的な双方向コミュニケーションへの転換点とも言える、とそんな空気感が漂っているみたい。実はそうでもなくて…と言いたいところだけど、この調査ではそう示唆されてるし、とりあえず現状そんな感じかな。
本項の出典:
- スマートSegmentation パーソナライズされたB2Bマーケティング
Pub.: 2025-07-08 | Upd.: 2025-07-08 - B2Bマーケティングを革新!ターゲットパーソナライゼーション戦略 ...
Pub.: 2025-03-06 | Upd.: 2025-03-07 - B2Bマーケティング — 戦略とガイド | アドビ
Pub.: 2022-07-22 | Upd.: 2025-03-03 - 【プロが解説】AIマーケティング最前線:2025年版 データ起点の ...
Pub.: 2025-04-12 | Upd.: 2025-06-16 - B2Bセールスパーソナライゼーションを活用して成果を高める方法
フォローアップ抜けに要注意、一連体験設計思考
広報活動のあとって、なんでだろう、アンケート回収や二次質問の受付みたいなフォローアップ設計を忘れがちになるんだよね、と専門家がぽつりと言っていた。ああ、わかる気もする。まずは情報を発信したら、その直後から短い期間内にまた連絡がとれるような流れを最初から決めておくこと、それとQ&A窓口も事前に用意しておく方がいいらしい。まあ、いつも全部うまくいくわけじゃないし、途中で他の業務に気を取られてしまったり…あっ、今何の話してたっけ?そうそう、本題は再接触フロー。
それで例えばだけど、社内イントラネット上で意見投稿フォームを設置して、一週間ごととか一定期間ごとに投稿内容をまとめて公開する運用も実際あるんだとか。不思議とこういう仕組みって誤解や妙な不安の連鎖も抑えてくれるし(人間ってすぐ疑心暗鬼になるから)、組織への信頼維持にも地味だけど効いてくるんじゃないかなと思う。ま、そんな完璧にはいかないものだけどさ。
それと、一斉配布型で終わらせちゃうんじゃなくてね、それぞれ受け手ごとの追加対応策――たとえば個別説明会とか、小さいグループごとのディスカッション――そこまで考えておいた方が『みんな同じ情報だから安心』っていう幻想から抜け出しやすい気がするんだ。でも、この「全員同じ情報=安心」って本当に正しいのかな…いや、違うかもしれないよね。
それで例えばだけど、社内イントラネット上で意見投稿フォームを設置して、一週間ごととか一定期間ごとに投稿内容をまとめて公開する運用も実際あるんだとか。不思議とこういう仕組みって誤解や妙な不安の連鎖も抑えてくれるし(人間ってすぐ疑心暗鬼になるから)、組織への信頼維持にも地味だけど効いてくるんじゃないかなと思う。ま、そんな完璧にはいかないものだけどさ。
それと、一斉配布型で終わらせちゃうんじゃなくてね、それぞれ受け手ごとの追加対応策――たとえば個別説明会とか、小さいグループごとのディスカッション――そこまで考えておいた方が『みんな同じ情報だから安心』っていう幻想から抜け出しやすい気がするんだ。でも、この「全員同じ情報=安心」って本当に正しいのかな…いや、違うかもしれないよね。