まあ、よく言われる「普及しない理由」
はい。まず、もう耳にタコができるくらい聞くのが、やっぱり「導入コストが高い」っていう話。 まあ、そりゃそうですよね。自動運転のトラクターなんて、家一軒買えるくらいの値段がすることもあるって聞きますし。 個人で、しかもそんなに規模が大きくない農家さんが「よーし、明日から導入だ!」とは、なかなかならない。これはすごく分かります。
で、次に来るのが「ITリテラシーの問題」。特に、今の日本の農業を支えているのが、まあ、ご高齢の方々が多いわけです。 2020年のデータでも、基幹的農業従事者の平均年齢が上がり続けてるっていう話もありますし。 そんな中で、「さあ、今日からこのタブレットで水管理してください」って言われても、ちょっと、いや、かなりハードルが高い。 スマホだって最近やっと慣れたのに、みたいな。これも、うん、確かにそうだろうなと。
あとは、そもそも論として、中山間地とかだと「電波が届かない」みたいなインフラの問題もありますよね。 IoTだ、クラウドだって言っても、ネットに繋がらなきゃただの箱ですから。こういう物理的な制約も、もちろん大きな壁です。
でもね、正直、僕はこういうのって、問題の「半分」しか見てないんじゃないかなって思うんですよ。お金やスキルの問題って、時間が経てば、技術が安くなったり、もっと使いやすいものができたりして、ある程度は解決するかもしれない。でも、もっと根っこにある、構造的な問題があるんじゃないかなって。今日はその話をしたいんです。
本当の理由①:致命的な「サイズのミスマッチ」
これが一番大きいと思うんですけど、今のスマート農業の技術って、実は「大規模農家」向けに作られてるものがほとんどなんですよね。 例えば、農研機構っていう、まあ国の研究機関みたいなところの実証実験でも、水田作の8割は20ヘクタール以上の大規模農家が対象だったりするんです。
考えてみてください。日本の農家さんって、法人化してすごく大きくやっているところもある一方で、家族経営で、そんなに広くない畑を丁寧にやっているところがたくさんあるわけです。 それなのに、提供される技術は、まるでアメリカの広大なトウモロコシ畑を走るような、巨大なコンバインみたいなものばかり。それじゃあ、日本の、あの、ちょっといびつな形をした、こぢんまりとした畑には、そもそも入っていけない。物理的にも、コスト的にも。
これって、軽自動車しか止められない駐車場に、大型トラックを無理やり入れようとしてるようなもんですよ。そりゃ無理だって話で。三菱総合研究所のレポートでも、この「規模の拡大・集約」がまず先じゃないかって指摘されてて、本当にその通りだなって思います。 技術の前に、それを受け入れる側の「畑のサイズ」が合ってない。このミスマッチが、普及を阻むすごく大きな、でもあまり語られない壁なんじゃないでしょうか。

本当の理由②:「データはあるけど、それで?」という“宝の持ち腐れ”問題
次に、これも根深い問題です。スマート農業って、結局は「データを集めて、それを活用する農業」ってことだと思うんです。 センサーで温度や湿度、土壌の水分量を測って、ドローンで葉っぱの色を見て生育状況をチェックして…。で、データは集まる。グラフとかも出てくる。でも、問題は「そのあと」なんです。
「はい、これがあなたの畑のデータです」って渡されても、多くの農家さんは「はあ、そうですか…で、具体的に何をすれば?」ってなっちゃう。 それはITリテラシーがないとかそういう話じゃなくて、データを「解釈」して「次のアクションに繋げる」っていう、これ、もうデータサイエンティストの領域なんですよね。農家は作物のプロであって、データのプロじゃない。この「翻訳者」がいないんです。
しかも、追い打ちをかけるように、メーカーごとに規格がバラバラだったりする。 A社のトラクターで集めたデータと、B社のドローンで撮ったデータがうまく連携できないとか。これじゃあ、せっかくのデータも断片的なままで、全体像が見えてこない。結局、一つ一つの機器は「スマート」かもしれないけど、農業経営全体としては「スマート」になっていかない。この、データのサイロ化も深刻な問題です。
要するに、スマート農業へのアプローチって、いくつか段階があると思うんですよ。ちょっと表にまとめてみましょうか。
| アプローチ | やること | メリット | 向いている人 | 個人的なツッコミ |
|---|---|---|---|---|
| 全部入り自動化 | 高価なロボットトラクターや自動収穫機を導入。人の作業を機械に置き換える。 | 劇的に省力化できる。規模が大きいほど効果大。 | 超大規模な農業法人。資金力があるところ。 | まあ、これができるのは一握りですよね。宝くじ当たるようなもん。 |
| データ活用・判断支援 | センサーやドローンでデータを収集。栽培管理の「判断」を支援する。 | 今ある設備を活かせる。品質向上や収量アップに繋がりやすい。 | 自分で考えるのが好きな、中規模以上の意欲的な農家。 | 一番の問題は「で、このデータ見てどうすんの?」ってなるところ。分析の伴走者が必要。 |
| サービス利用(シェアリング) | ドローンでの農薬散布やデータ解析などを、専門業者に作業委託する。 | 初期投資がほぼゼロ。必要な時に必要な分だけ使える。 | 小〜中規模農家。機械の維持管理をしたくない人。 | これが一番現実的かも。でも、近所に頼める良いサービス事業者さんがいるかどうかにかかってる。 |
本当の理由③:「支援はあるけど、届かない」という支援のパラドックス
「コストが高いなら、補助金を使えばいいじゃない」って声も聞こえてきそうです。確かに、国や自治体はたくさんの補助金を用意しています。 農林水産省も「スマート農業技術活用促進法」なんて法律を作って、税金を安くしたり、お金を借りやすくしたり、いろいろ後押ししてるんです。
でも、ここにも大きな落とし穴がある。その補助金の申請手続きが、めちゃくちゃ複雑だったりするんです。 事業計画書を書いて、何枚も書類を用意して…。これって、日々の農作業で忙しい、特に小規模な農家さんにとっては、ものすごい負担です。結果的に、書類仕事が得意な、体力のある大規模な法人が補助金を活用しやすくて、本当に支援が必要な人に届きにくい、というパラドックスが起きているように感じます。
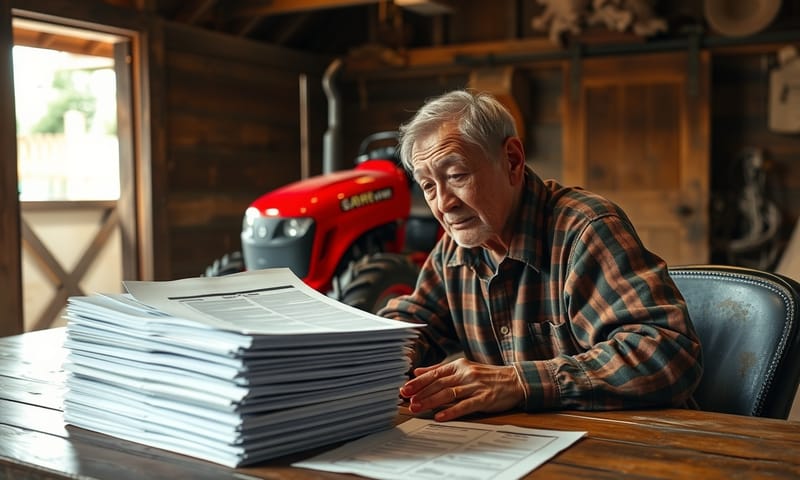
ここでちょっと、海外の話も見てみると面白いんです。アメリカみたいな国だと、とにかく広大な土地で効率を上げるための技術が中心になりますよね。でも、Terra Drone社のレポートなんかを見ると、アジア地域では「断片化された小規模な農地」がスマート農業普及の大きな障壁になっていると指摘されています。 これ、すごく日本の状況と似ています。ただ、日本がさらに難しいのは、その担い手の高齢化が世界でもトップクラスに進んでいること。 だからこそ、単に技術を提供するだけじゃなくて、申請手続きの簡素化とか、地域ごとに相談できる窓口とか、そういう「使えるサポート体制」が、海外以上に重要になってくるはずなんです。
じゃあ、これからどうすればいいのか?
ここまで話してきたように、問題の根っこは、単なる「機械の値段」や「パソコンが使えるか」じゃないと思うんです。じゃあ、どうすればいいのか。僕が思うに、3つの方向性があるかなと。
一つは、さっきの表でも書いた「農業支援サービス」を育てること。 農家さん自身が全部の機械を買って、使いこなすんじゃなくて、専門の業者が地域を回って、ドローンを飛ばしたり、データを分析してくれたりする。いわば「スマート農業の出前」ですね。これなら、農家さんは初期投資なしで、一番おいしいところだけを使える。
二つ目は、「身の丈にあった技術」の開発です。 三菱総研のレポートでも「中規模農家向けの“身の丈にあった”機械開発が重要」と書かれています。 まさにその通りで、F1カーみたいなハイスペックマシンだけじゃなくて、もっとシンプルで、価格も手頃な、「軽トラ」みたいなスマート農機がもっと出てくるべきなんです。完全自動じゃなくても、ちょっと作業をアシストしてくれるだけで、現場はすごく助かるはずですから。
そして三つ目が、教育ですね。ただし、これはPC教室みたいな操作方法の教育じゃない。集まったデータをどうやって「経営判断」に活かすか、という思考法を教える教育です。地域のJAさんとか普及指導員の方が、農家さんと一緒にデータを見ながら「じゃあ来週は、ここのエリアだけ水を少し多めに撒きましょうか」みたいに、伴走してくれる体制が作れたら、景色はかなり変わってくるんじゃないかなと思います。

結局のところ、スマート農業が普及しない本当の理由は、「スマート」の部分がすごすぎるんじゃなくて、それを受け止める「農業」の側の構造…つまり、農地の規模、経営のやり方、そしてサポートのあり方が、まだ新しい技術に追いついてないってことなんだと、僕は思っています。
技術はあくまで道具ですからね。その道具を、誰が、どうやって使うのか。その「使い方」の仕組みをデザインすることのほうが、実はもっと大事なのかもしれませんね。
さて、長々と話してしまいましたが、最後に皆さんに一つ質問です。もしあなたが農家で、100万円の補助金をもらえることになったら、「高性能なドローンを1台買う」のと、「5年間使えるデータ分析と栽培相談のサポートサービスを契約する」の、どちらを選びますか? よかったら、その理由も一緒に教えてもらえると嬉しいです。



